執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
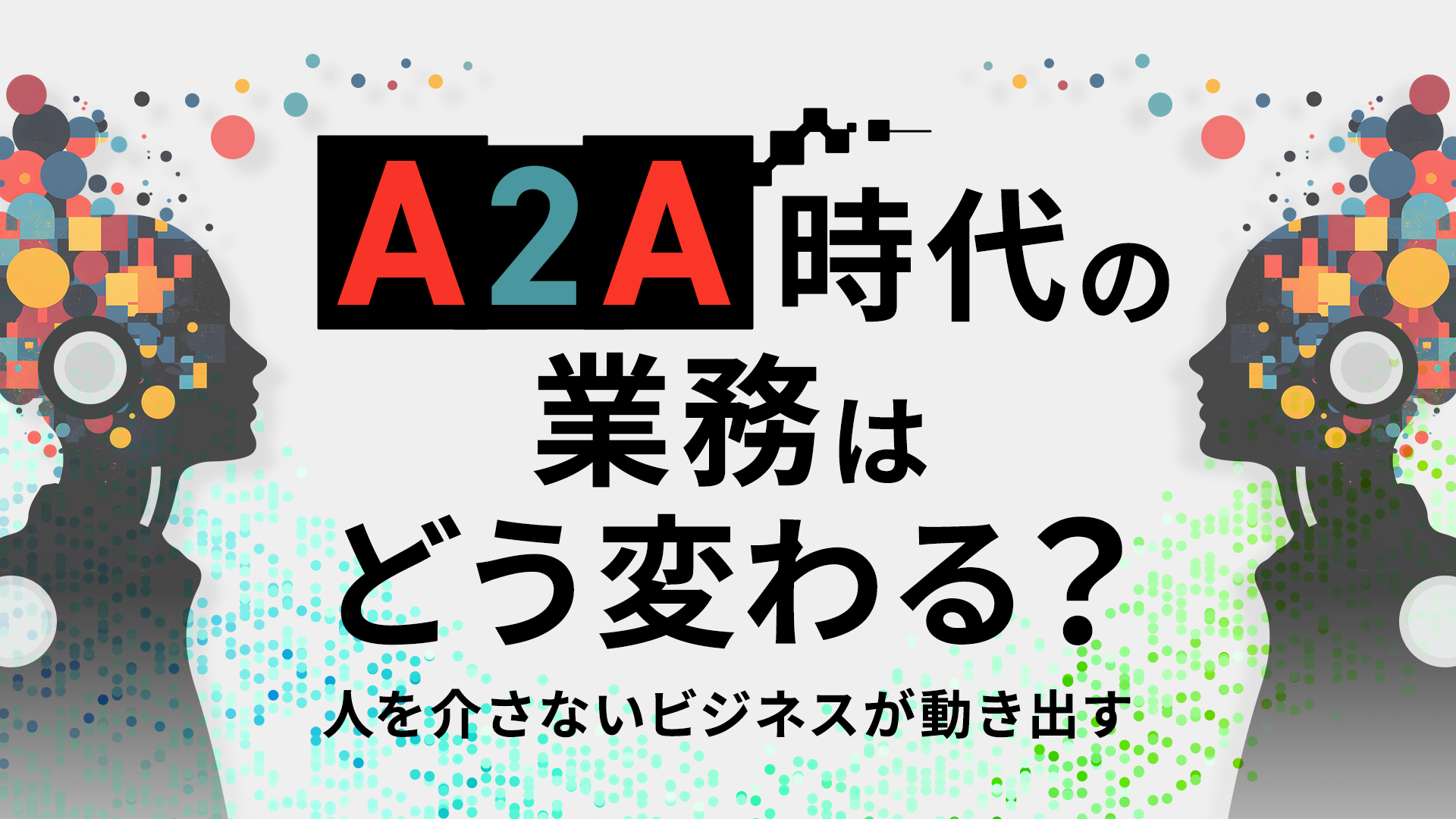
AIを活用した業務効率化は、顧客対応や帳票作成といった部分業務を中心に、多くの企業で導入が進んでいます。しかし、こうした個別最適の積み重ねでは、業務全体を自律的に連携・遂行できる構造には至っていないのが現状です。こうした状況のなかで、次に問われるのは「AI同士がどう連携し、業務を動かすか」です。
そこで注目されているのが、AI同士が情報をやり取りし、交渉・合意・契約・実行までを自律的に完結させる構造―A2A(Agent to Agent)です。この言葉は、一般的にはAI間連携の総称としても使われており、たとえばGoogleのA2A Protocolはその一実装例(通信標準化仕様)です。本記事では、AIエージェントが業務構造をどのように変えるのか、特にA2A(AI-to-AI communication)に焦点を当てて解説します。
A2Aと似た概念にMCP(Model Context Protocol)がありますが、MCPはエージェントと外部ツールの連携が目的であることに対し、A2Aはエージェント同士の連携を促すことが主目的です。
こうしたAIエージェント連携の流れが加速するなかで、Googleが2025年4月に発表した「A2A Protocol」が登場しています。このプロトコルは、HTTPやSSE、JSON RPCといった標準技術をベースに構築されており、開発元や機能の異なるAIエージェント同士が共通言語でやり取りできる環境を整備しています。まだ商用化の初期段階ではありますが、Microsoft、SAP、Salesforceなど100社以上が賛同しており、2025年6月にはLinux Foundationに寄贈され、ベンダーニュートラルな形での標準化に向けて進んでいます。
このように、業務の自動化は「AIを使う」段階から、「AI同士が連携し合う」段階へと進みつつあります。A2Aとは、まさにその構造転換を実現する鍵となるコンセプトなのです。
多くの企業では、AIを活用した業務の効率化が進んでいます。たとえば、チャットボットによる問い合わせ対応や、レポート作成を自動化するAIエージェントの導入などは、その代表例です。しかし、こうしたエージェントはあくまで単体で機能しており、業務全体の視点では依然としてプロセス間の分断が残されています。
なかでも顕著なのは、業務プロセスの接続部において人による介在が不可欠となる場面です。たとえば、顧客の質問に自動応答するAIが存在していても、その後の在庫確認や配送手配は別システムで管理されているため、エージェント間の連携が成立せず、結果的に人間が処理を引き継いでいく必要があります。
こうした分断が生じる背景には、AIエージェント同士が情報を交換・連携するための共通言語や通信プロトコルが整備されていなかったことがあります。そのため、複数のエージェントが存在していても、業務プロセス全体が一貫して自動化されるには至らず、「AIを導入しても人の作業が減らない」という状況に直面している企業も少なくありません。A2Aは、まさにこの問題を解決するために登場した、AI同士の連携を前提とした新しい業務設計のアプローチとして注目されています。
近年のAIは、テキスト生成、翻訳、感情分析、契約書作成など、特定業務に特化した専門エージェントへと進化してきました。しかし、どれだけ個々の能力が高くても、相互に連携できなければ、全体の業務プロセスは自動化されません。
A2Aは、このようなサイロ化されたAIエージェントをチームとして機能させる構造です。エージェントはもはや孤立したツールではなく、連携しながら業務全体を自律的に進める仲間へと進化しつつあります。A2Aの本質とは、業務を部分ではなく構造全体として最適化するための仕組みにあるのです。
A2Aは、もはや構想段階にとどまらず、一部の企業や業界で実装・検証が始まっています。その兆候は、複数の国際調査や展望にも表れています。たとえば、世界経済フォーラム(WEF)は2025年、「エージェント型ビジネス革命(Agentic Business Revolution)」という表現で、AIが目標を自律的に設定し、遂行する「コグニティブ・エンタープライズ」への移行を提唱しています※3。
また、Gartnerの調査(2025年5月)によれば、CIO・ITリーダーの24%がすでにAIエージェントを12体未満導入済み、4%が12体以上導入済みと回答。さらに50%が現在調査・実験中で、2026年末までの導入を予定している企業も17%にのぼります※4。
国内でも、野村総合研究所が、日本企業で2030年までに180万〜900万体のAIエージェントが導入されると試算しました。ただし、本格的な人手不足解消に向けては、技術的な成熟と導入戦略の整備が不可欠と指摘しています※5。このように、A2Aは「AI技術の延長線」ではなく、業務や経営構造そのものを変えるパラダイムとして、現実の選択肢になりつつあるのです。

AIによる業務自動化は、多くの企業ですでに導入が進んでいます。ただし、RPAや単体AIでは業務の一部を効率化できても、プロセス全体をつなげて自律的に進めるには至っていません。本章では、A2Aによって何がどう変わるのか、調達・契約・交渉といった具体業務をもとに解説します。また、すでに動き出している実装事例を取り上げ、A2Aを構想ではなく、実装フェーズにある構造として捉えます。
これまでのAI導入は、営業、調達、カスタマーサポートといった各部門単位での業務効率化にとどまっていました。A2Aでは、複数のエージェントが横断的に連携し、それぞれの専門性を活かして協働することで、業務全体を一気通貫で処理できるようになります。
たとえば調達業務では、AIエージェントが在庫状況や需要予測から発注の要否を判断し、複数のサプライヤーと同時に価格交渉をおこないます。続いて、納期や品質条件を踏まえて最適な調達先を自動で選定し、契約書の作成・締結から発注処理までを一貫して完了させます。
こうした完全自律型の調達プロセスは、すでに現実味を帯びています。A2Aは、単体のAIに業務を任せる段階から、複数のエージェントが連携し、役割を分担しながら業務全体を動かすフェーズに進みつつあります。
A2Aはまだ初期段階にありますが、すでに一部の先進企業や研究機関において、実証および実装フェーズに移行しつつあります。たとえば、金融大手Moody’sでは、信用格付やリスク分析の領域において、複数のAIエージェントが分担・連携しながら業務を遂行する体制を構築しています。リスク情報のリアルタイム監視を担う「ReconAI」では、エージェント群が常時市場データを分析し、異常シグナルを検出。
一方、「CrewAI」では信用分析やレポート作成を複数のエージェントが分担し、人間は最終レビューのみを担う構造となっています。判断精度の担保に向けては、複数の大規模言語モデル(LLM)による投票制や、RAGスコアによる自動評価手法が導入されています。
また、スタンフォード大学による研究では、AIエージェント同士が交渉をおこなう価格決定モデルを用いた実験がおこなわれ、エージェントの能力差によって交渉結果に明確な格差が生じることが実証されました。具体的には、能力の低い買い手エージェントは約2%高く支払い、能力の低い売り手エージェントは最大で14%もの利益を失う結果となっています。これは、A2A構造においてエージェントの設計と学習の質が、ビジネス成果に直結することを示す重要な示唆です。
A2Aによって業務構造が再設計されるなか、企業にとっての競争優位性の源泉もまた変わりつつあります。これまでのように、人材や単体のAIの能力だけでは成果に直結しづらくなっています。「どんなエージェントを持つか」ではなく、「それらをどう連携・交渉・統率させるか」という、構造全体を設計する力です。A2A時代の競争戦略をテーマに、エージェント連携設計の重要性と、企業が備えるべき組織体制や人材の方向性について整理します。
これまで企業の競争力は、優れた人材を確保し、適切に配置することにかかっていました。AI時代には、優秀なAIエージェントを導入・育成することが新たな差別化の軸になります。そして、A2Aは、その競争をさらに一歩先に進めます。問われるのは、「どれだけ優秀なAIを持つか」ではなく、「それらをどう連携・交渉させるか」という構想力です。
たとえば、企業間交渉では、発注側のエージェントが価格戦略を担い、契約交渉エージェントが合意形成を主導し、リスク管理エージェントが条件をリアルタイムで監視・補正するようになります。このように、複数のエージェントが役割を分担し連携する仕組みそのものが成果に直結するのです。
AIをチームメンバーのように育て、成果に結びつけるには、企業内部の体制設計と学習環境の整備が欠かせません。米国のRPA大手、Automation Anywhereは、A2A時代に必要な組織設計として次の2点を提言しています。
ひとつは、社内スキルマーケットプレイスの整備です。従業員が異なる機能領域のプロジェクトに柔軟に参加し、自らの業務知識や判断ロジックをAIエージェントに移植・適用する経験を積むための仕組みです。通常の所属部門を越えた環境でスキルを実践的に試すことで、業務知識をAIに落とし込む方法論を、組織内で共有・更新していく役割も担います。
もうひとつは、外部機関との連携による専門スキルの体系的習得です。プロンプト設計、ガバナンス構築、エージェント評価といった高度スキルを、教育機関やトレーニングプロバイダーを通じて組織的に取り込む体制が求められます。
PwCの調査によれば、AIエージェントを業務に統合することで、生産性や意思決定の質が各部門で20〜30%向上する可能性があると報告されています。こうした成果は限定的な効果にとどまらず、組織全体の構造変革へと波及する点が特筆されます。このような変化のなかで、人間に求められる役割も大きく転換します。
従来は、AIにタスクを与え、実行結果を受け取るという関係に過ぎませんでした。しかしA2A時代には、複数のエージェントを設計・統率し、業務全体を動かす構造を俯瞰する立場が求められます。たとえば、次のような関りで仕組みを考えていかなければなりません。
このように、AIを活用する側ではなく、動かす側としての力が、今後のマネジメントにおける重要な資質になるのです。

ここでは、A2A導入に向けた現実的な進め方として、構想の設計、リスクの見極め、そして第一歩をどう踏み出すかを整理します。
A2Aはいきなり全社に適用するのではなく、まずは「どこから設計を始めるか」「何から委ねるか」を明確にし、段階的に範囲を広げていくことが現実的です。社内に根づかせるためには、技術的な要素だけでなく、構造設計・責任設計・評価設計の3点をセットで考える必要があります。
ここまで見てきたように、A2Aは極めて魅力的な構想ですが、「ツールを導入すれば業務全体が自動化される」といった安易な期待は禁物です。Gartnerは、日本企業の約60%が将来的にエージェント型AIやヒューマノイドとの協働を前提としたビジネスに移行すると見通す一方で、「2027年までにA2Aを含むプロジェクトの40%以上が見直しに直面する可能性がある」と警鐘を鳴らします。その主な要因として、次のような課題が挙げられています。
A2Aは、AIの技術的進化ではなく、業務構造そのものを再定義する取り組みです。その本質を捉えずに導入を進めることは、成果を伴わない投資に終わるリスクをはらんでいます。
A2Aの導入に向けては、構想と並行して、業務・技術・体制の実態を的確に把握することが不可欠です。以下の4つの視点から現状を点検することで、PoC(概念実証)から本格導入への実行計画が現実味を帯びてきます。
視点1:業務の棚卸し
A2Aにより自律化が可能な交渉・契約・実行プロセスを洗い出し、既存業務とのギャップを明確化する
関連コラム:「業務フローの棚卸し」から始めるAI時代のBPR再入門
視点2:技術環境の確認
API連携やデータ構造の整備状況、エージェントの評価体制といった実装基盤を点検する
視点3:体制の構築
IT・業務・法務・セキュリティの連携によるクロスファンクショナルな推進チームを組成する
視点4:スモールスタートの実践
PoCを通じてスケーラビリティやガバナンス上の課題を早期に抽出し、段階的に展開する
A2Aの導入には、特定の技術選定ではなく、いかに業務構造全体を設計し直すかが問われます。いまから、AIの配置や連携について構想することが、次の競争力を築く第一歩になります。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。