執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
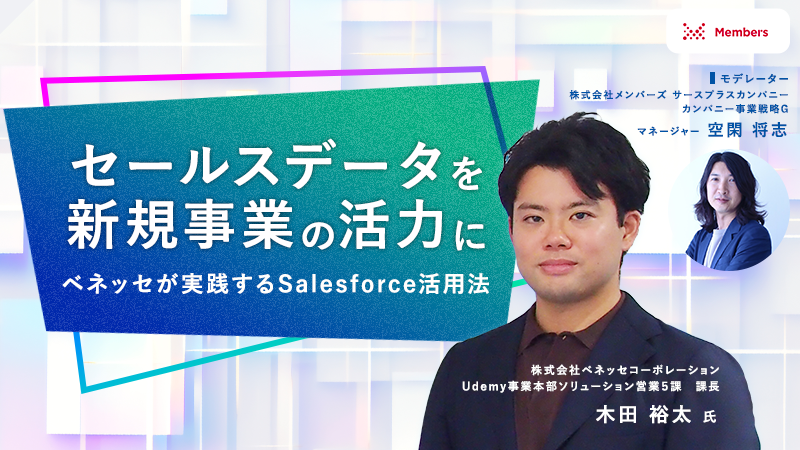
「Salesforceを導入したものの成果が上がらない」「Salesforceについて相談できる相手がいない」といった悩みを抱えている方は少なくありません。多くの企業が運用保守を外部パートナーに依存し、Salesforceの利活用に関する実践的なアドバイスを受けられずにいます。特に、機能改修の提案を受けても社内に知見がないため、どれが良い提案か判断できずに困っている企業が多いのが現実です。
そのようななかで、ベネッセコーポレーションはどのようにSalesforceを活用し、新規事業の活力へと結びつけたのでしょうか。本記事では、2025年2月にベネッセコーポレーションの木田裕太氏をお招きし、Salesforceの効果的な活用法についてお話しいただいたオンラインセミナーの内容を一部抜粋してご紹介します。
 株式会社ベネッセコーポレーション
株式会社ベネッセコーポレーション
Udemy事業本部ソリューション営業5課 課長
木田 裕太 氏
集合研修事業やアセスメント事業の立ち上げに際しセールス、マーケティングをリード。ベネッセとしてお客さまの課題解決に向け包括的に支援可能な営業組織の構築に従事。
 株式会社メンバーズ サースプラスカンパニー
株式会社メンバーズ サースプラスカンパニー
カンパニー事業戦略G マネージャー
空閑 将志
広告代理店にて大手酒類メーカーのDtoC・CRMの支援を担当後、動画配信SaaSベンチャー企業にてカスタマーサクセス部門の立ち上げ、動画SNSマーケティング事業責任者として従事。2023年9月にメンバーズ サースプラスカンパニーに参画後、Salesforceの利活用支援を担当。2024年11月より現職。
当社がSalesforceを導入した背景には、事業ドメインの変化が大きく影響しています。
2015年、米国Udemy社と包括的業務提携契約を締結し、オンライン動画学習プラットフォーム「Udemy」の国内展開を開始しました。2019年には、法人さま向けの定額サービスである「Udemy Business」の提供を開始し、「最終学歴」以上に「最新学習歴」を誇れる社会の実現を目指して事業を展開していくなかで、個人の自己実現や人事支援へのニーズが高まったことを受け、ラーニング領域からHR領域へと事業を拡大しました。
その結果、周辺商材の開発やアライアンス、M&Aなどによりサービスラインナップが拡充し、Udemyの単一事業から複数事業を展開する体制へと変化しました。
Udemy事業のみを展開していた時期は、米国Udemy社のSalesforceを間借りして営業管理をおこなっていましたが、そのなかに当社サービスを組み込むことは難しく、事業ポートフォリオの拡大に伴い、Salesforceの導入が不可欠となりました。
新規事業立ち上げ当初は、Udemy社のSalesforceを間借りできなかったため、約1年間スプレッドシートで案件管理をおこなっていました。しかし、スプレッドシートでは営業履歴が上書きされるため、各ステータスで何が起こっているのか把握することが困難でした。ステータスも上書きされ、最終的な商談結果しか分からないため、一面的かつ静的な営業管理であると言わざるを得ません。
またSalesforce導入の大きな目的は、新規事業・サービスの立ち上げにおける課題、特に「売れない」という現象の理由を明確にすることであり、その後の事業成長に大きく影響すると考えています。

新規事業の立ち上げにおいて「サービスが売れない」という課題に直面した場合、顧客認知の形成、初回商談の内容、2〜3回目の商談、受注に至った要因など、さまざまな情報が事業成長に不可欠なデータとなります。Salesforce導入により、これらの情報を一元管理できることが導入に踏み切った要因の一つとなりました。
各営業フェーズにおける顧客からのフィードバックは、さまざまな解釈が可能です。例えば、「現在のサービスよりも機能が劣る」「代替するほどの価値がない」「費用が高い」といった意見が出た場合、営業スクリプトの問題なのか、営業活動の問題なのか、製品改善が必要なのか、といったさまざまな角度で要因を分析する必要があります。製品の問題であるにもかかわらず、営業の問題として捉えがちですが、実際は両方の要因が複雑に絡み合っているか、多面的に存在していることが多いです。
また初回商談は順調だったにもかかわらず、2、3回目の商談で失注したケースなどの場合、各商談フェーズにおける顧客の反応を詳細に分析するために、フェーズごとのやり取りを動的に記録する必要があります。そのため、Salesforceの特徴である可変性とデータ格納量が不可欠です。
つまり、従来の一面的かつ静的な営業管理から脱却し、商談フェーズや製品、営業活動など、さまざまな角度から顧客の反応を動的に把握することが目的でした。

Salesforce導入にあたり、メンバーズさんとの最初のやり取りで「ベネッセさまはどのようなビジョンをお持ちですか」という質問を受けたことを今でも覚えています。質問の重さに戸惑いもありましたが、その後のセッションを通じて、法人としての顧客への提供価値、事業規模の目標などを深く掘り下げていただきました。導入前の約6ヵ月間、要件定義などのセッションは40回を超え、詳細な定義・設定がおこなわれました。
特に価値が高かったのは、要件定義フェーズでの支援です。事業把握の段階では、メンバーズさんから「ベネッセさまはマーケットリーダーを目指すのか」「特定のニーズに応えていく事業戦略なのか」「シェアを取りたいのか」といった質問が繰り返され、当社が目指す方向性を深く理解しようと努めていただきました。
事業の深い理解に基づき、「顧客はどのような人物像か」「どのようなストーリーをもってサービスを購入するのか」「顧客は各商談フェーズにおいてどのような状態にあるべきか」「その状態に至るためにはどのような情報伝達が必要か」といったペルソナ・バイヤーズジャーニーマップを作成しました。またKPI設計では、「どのようにマネジメントしたいのか」「事業目標達成のためにどの指標を見るべきか」といった問いを通じて、最適なKPIが設定されました。
さらに、KPIに基づいて商談フェーズを定義しました。顧客の状態を起点として商談フェーズが定義され、各フェーズにおける顧客の状態が詳細に定義されることで、次のフェーズに進むための必要な条件が明確になりました。
まとめると、要件定義フェーズにおいて、メンバーズさんは当社の事業を深く理解し、事業成長に貢献するさまざまな成果物を提供していただきました。なかでも、当社が認識していなかった機会点やリスクを指摘いただいたことは、多面的かつ動的な営業管理を実現する質の高いサポートであると感じています。Salesforceの導入ベンダーというよりは、新規事業の立ち上げを支援するコンサルタントとして、メンバーズさんには伴走いただきました。
参考:Salesforce利活用促進・セカンドオピニオンサービス(コンシェルジュBX)

営業現場へのSFAの浸透は、私自身もまだ改善の余地があると感じていますが、これまでにおこなってきた取り組みをご紹介します。
Salesforceへの情報入力の現場浸透は、SaaS・IT全般で共通する課題だと考えており、マインドや風土、雰囲気の醸成だけではなく、能力開発やスキル開発、組織開発もセットでおこなう必要があります。ITツールの導入は、ハードとソフトの両面からアプローチする必要があるといわれていますが、まさにその通りだと思います。
導入前からキーパーソンを議論に巻き込み、要不要な項目やプロジェクト予算などについて合意を得ている状態を組織の目標として設定しました。そのうえで、将来を見据えた理想的な営業管理体制を構築するというマインドセットを図りました。
新規事業は不確定要素が多く、KPIも試行錯誤しながら設定する必要があります。そのため、現時点でのKPIは暫定的なものであり、今後の改善が不可欠であるということを営業メンバーに伝えていました。
また、営業管理でSalesforceを使用しているにもかかわらず、事業業績や案件管理を手元のExcelでおこなっている場合、Salesforceは単なる入力ツールとなってしまいます。そこで、Salesforceのダッシュボードやレポート機能の活用を徹底し、可能な限りSalesforceを起点としたコミュニケーションを心がけました。慣れこそ最大の武器であると考え、マネージャーを含めた組織全体で意識改革をおこないました。
営業DXによって得られる成果やメリットを理解することは、Salesforce導入だけでなく、これからの時代のビジネスパーソンとして必要であり、スキルアップにもつながります。そのため、Salesforce導入の意義における意識改革と、DXの重要性やデータの価値といったスキル習得の両面を重視し、導入から実行まで進めていきました。しかし、チーム全員がこのマインドセットを共有できているわけではないため、今後の課題はこの意識をいかに広げるかという点にあります。
Q.他にも同様のサービスがあるなかで、Salesforceを選んだ決め手は何でしょうか?

木田氏
率直に申し上げますと、以前から米国Udemy社でSalesforceを使用していたことが大きな理由の一つです。Udemyの業績データも含めた連続的な管理が重要な要素だったため、大きなアドバンテージとなりました。
もう一つは、既存のCRMツールとの互換性、スピーダなどの企業データベースとも接続できる拡張性です。加えて、商談フェーズごとの情報整理・入力における柔軟性や可変性も重視し、Salesforceを選定しました。

空閑

木田氏

空閑

木田氏
Q.見える化だけで終わらせないために、Salesforceをどのように活用すればいいでしょうか?また有益な情報を集約するための活用事例をお伺いしたいです。

空閑

木田氏

空閑
営業支援や事業推進、DXなどに取り組むなかで、メンバーがなかなかSalesforceを利用しないことに頭を悩ませている方もいらっしゃると思います。ベネッセさんは会議の場面などで、Salesforceを使ってどのようなコミュニケーションを取っているのでしょうか?

木田氏
例えば、業績や進捗を確認する際にはSalesforceの画面を投影し、「この案件が数日動いていないが、状況はどうなっているのか」など、Salesforce上でコミュニケーションを取っています。
また、Salesforce内に営業担当者が週内に入力した内容を確認できるレポートがあり、それを私は頻繁に見ています。レポートへのコメントや「次回はどのようなアクションを起こそうと思っているのか」「このお客さまの声はプロダクトチームに共有しよう」といった細かな情報交換もSalesforceのChatter機能を活用しています。

空閑

木田氏
Q.Salesforce導入後、社内に定着させるためのロードマップはどのように構想したらいいでしょうか?Salesforceの利用を活性化させるために工夫したことはありますか?

木田氏
ご質問の意図とは少し異なりますが、導入前から関係者の協力を得ることが重要です。
新規事業におけるセールスデータの必要性を事前に合意した上で、Excel管理だけでは不十分であるという共通認識を持つように努めました。管理方法について悩むなかで、1〜2ヵ月後にSelesforceの導入が決定したことを伝えると「待ってました」と喜んでもらえ、その後の導入もスムーズに進みました。このように、導入前から丁寧に仕込むことが重要だと考えています。
次に、社内に定着させるためのロードマップの構想についてですが、やはりマインドと風土醸成、スキル開発をセットで取り組んでいくことに尽きると思います。また、先ほど触れた通り、会議中にSalesforceの画面を投影したり、業務指示や依頼をSalesforce上でおこなったりすることで、メンバーも徐々に慣れてくれました。 明確なロードマップを立てるというよりは、段階的に浸透させていったというのが正直なところです。

空閑

木田氏

空閑

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。