執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
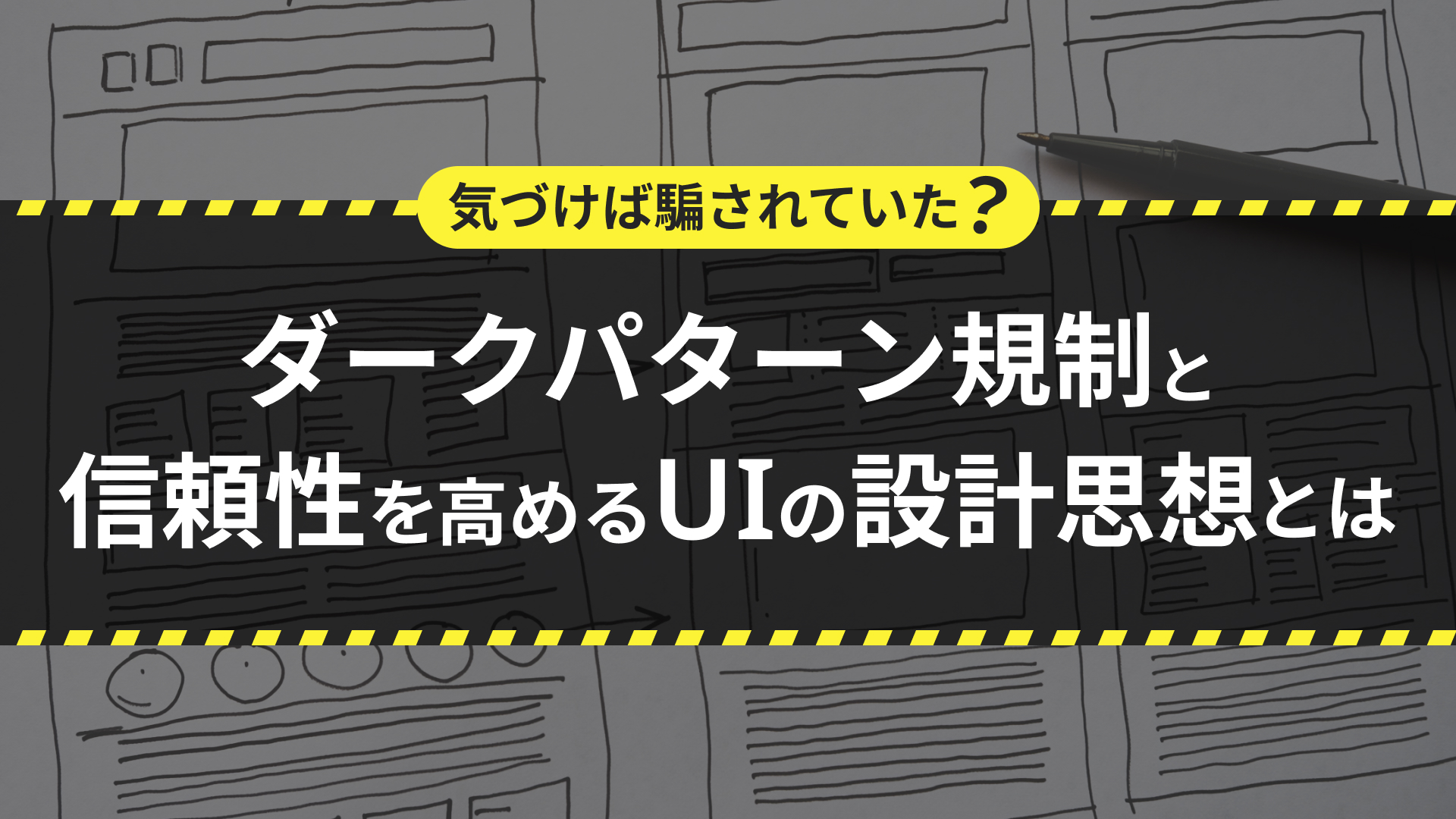
ユーザーに不利な選択を促す「ダークパターン」が、日本でも問題視され始めています。消費者庁などの警鐘もあり、UIの在り方が大きく問われる時代に入りました。
本コラムでは、代表的なダークパターンの例や海外の規制動向を紹介しつつ、企業が今見直すべきUI設計の視点から、ユーザーの信頼を損なわない「誠実なUX」とは何かを考えます。

現在、インターネットを使った消費行動として、多くの方がネットショッピングやサブスクリプションサービスを使うようになりました。その一方でWebサイトやアプリ上でユーザーの意図に反した行動を誘導する手法であるダークパターンが問題視されています。
例えば、メルマガ登録欄にあらかじめチェックが入っているサイトや、解約ボタンが見つけにくいサイトなどはほとんどの方が経験しているのではないでしょうか。この問題は、2025年3月に公表された、国民生活センターの「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」でも、ネット通販トラブルが起きる要因や課題として指摘されていました。
この調査では、9割以上が「未成年者本人の知識・理解が不十分であること」といった、未成年者がトラブルに巻き込まれている点や「事業者による年齢確認や保護者の同意を取る方法が不十分であること」、「不当表示やダークパターン等への規制が追い付いていないこと」も多数として取り上げていました※1。
当然ながら、ユーザーの不利益を前提としたUI設計は、信頼失墜や炎上リスクにつながります。これらの対策として一般社団法人ダークパターン対策協会は、2025年7月、ユーザーの意思決定を尊重する設計をおこなっていることを第三者が認定する制度「NDD認定制度」を創設しました※2。企業側もユーザーが安心してサービスを利用できる環境を整備する必要があり、自主的な対応を促す動きが進んでいます。
※1:出典「「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」調査報告<結果・概要>」(独立行政法人国民生活センター・2025)
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250305_1_1.pdf
※2:出典「誠実なWebサイトを認定する「NDD認定制度」における「自己審査チェックシート」と「認定マーク」、「ダークパターン・ホットライン」を公開」(一般社団法人 ダークパターン対策協会・2025)
https://www.ndda.net/post-non-deceptive-design/
ダークパターンの種類と仕組み、定義について改めて説明します。
独立行政法人国民生活センターが発行している「国民生活特集 消費者を欺くダークパターンとは」にて、“ダークパターンとはユーザーを騙し、人々の判断を誤らせるインターフェース”として定義されています。
そのため、ECサイトなどを運営する企業側は、意図せずにダークパターンを設計していないか注意を払わなければなりません。特にリーダー層は、そのUIの結果が、ユーザーの意思決定を歪めていないかという視点を持つことが重要です。企業にとってCVRやCTRを意識した設計が、ユーザーには誤認や不快感を与えてしまうものになっていないかを常に注視する必要があります。
主なダークパターンの種類とその事例を紹介します。こちらは独立行政法人国民生活センター「国民生活特集 消費者を欺くダークパターンとは」に掲載されている、2022年のOECD(経済協力開発機構)版を参考にしています※4。
主なダークパターンの種類とその事例
| 種別 | 説明 | 例 |
| 行為の強制 | 特定の機能にアクセスさせるため、ユーザーに不要な行動を強いる設計。ユーザーが拒否すると機能が使えなくなり、行為の強制をさせられます。 |
・商品購入時の会員登録が必須 ・ユーザーの同意なく連絡先情報を抽出 ・無料トライアル期間終了後、自動で有料モードに切り替わる |
| インターフェース干渉 | UIの見せ方でユーザーの選択を歪める設計。ユーザーを意図的に誤解させ、無意識のうちに不利な行動をとらせます。 |
・解約ボタンなどの重要な情報を視覚的に不明瞭にする ・都合の良い選択肢を初期表示として設定 ・虚偽の高値からの割引表示 |
| 執拗な繰り返し | ユーザーが拒否しても何度も同じ選択を迫られる設計。ユーザーはその煩わしさから企業側の要求を最終的に許可してしまうことがあります。 |
・ポップアップで「今だけ割引!」が何度も表示される ・ボタンの選択で「あとで」などが選べない、拒否の選択肢がない ・「レビューを書いてください」の通知が出て、書くまで消えない |
| 妨害 | ユーザーの望む行動を意図的に複雑化する設計。特定の行動をさせないために手続きを複雑化し、多くの手順を踏ませます。 |
・解約や退会手続きの導線がわかりにくい ・アカウント削除に電話やメールを必要とする ・商品の価格を異なる条件や単位で表示し、比較しにくくする |
| こっそり | ユーザーに気づかれないように意図に反して特定の行動を促す設計。意思決定に関連する情報を隠し、サイトやアプリのデザインでユーザーが不利な選択をするように仕向けます。 |
・メルマガ配信のチェックボックスが最初からオンになっている ・サブスクリプションが通知なく自動更新される ・勝手に手数料や送料が追加されている |
| 社会的証明 | 他人や架空の人物の行動を利用して、選択を誘導する設計。購入するつもりがなかった商品まで購入させるように誘導し、ユーザーの意思決定に影響を及ぼします。 |
・演出で書かれた架空の高評価レビュー ・「現在、〇〇人が閲覧中です」「○○さんがこの商品を購入しました」のような表示 ・根拠不明の「ベストセラー」の表示 |
| 緊急性 | 時間制限や在庫制限を演出し、焦らせる設計。緊急性があるかのように見せ、ユーザーにプレッシャーをかけて購入を促します。 |
・購入ボタンの近くのカウントダウンタイマー ・期間不明の「期間限定セール!」の文言 ・実際の在庫数ではない「残り3点」という表示 |
これらのダークパターンを取り入れたUI設計は、短期的には企業の利益につながるように見えますが、長期的にはブランドの信頼低下や法的リスクを引き起こす可能性があります。企業側は、上記のような操作性のUIになっていないかどうかを判断しながら設計しなければなりません。
ダークパターンについて、海外での規制状況と、日本の規制に関する動きも調査しました。
米国のダークパターンに関わる主な規制には、連邦取引委員会法「FTC法」が存在します。米国FTCがサブスクリプションサービスとプライバシー設定におけるダークパターンの使用実態を調査したところ、対象となったサイトとアプリの約76%が、少なくとも1つのダークパターンの可能性のあるものを採用し、約67%が複数のダークパターンの可能性のあるものを採用していたことが判明しました※5。
今後は、サブスクリプションや会員登録を解約する手続きは、登録するときと同じくらい簡単にしなければならないという新しい規則が導入される予定です※6。
EUでは、統一された定義や法律はまだ存在しないため※7、現在は主要な3つの法律や枠組みである、GDPR(一般データ保護規則)、DSA(デジタルサービス法)、UCPD(不公正取引行為指令)を組み合わせてダークパターンを規制していました※8。今後は、これらを統合し、ユーザーの判断を守るデジタルフェアネスの確立を目指しています。
また、実際に苦情を申し立てた例として、2025年6月、BEUC(欧州消費者機構)がアパレル大手SHEINを対象に、ポップアップ、カウントダウンタイマー、無限スクロール、頻繁な通知などのダークパターン使用を追及し、EUへ公式に苦情を提出しました※9。
特定商取引法、景品表示法、個人情報保護法などを通じて対応可能なケースもありますが、現時点で日本にはダークパターンそのものを直接規制する法律はありません。しかし、消費者庁も警鐘を鳴らしており、リサーチ・ディスカッション・ペーパーとして「いわゆる「ダークパターン」に関する取引の実態調査」の内容を公表していました※10。
なかにはダークパターンとして判断が難しいケースも目立ち、消費者の意思決定に与える影響についての実証実験が必要とされています。また規制は米国やEUの動きと整合性を取る必要があるため、今後は国際動向を参考にした制度整備が求められています※11。
ユーザーに誤認や誤誘導を生むようなダークパターンUIですが、必ずしも企業側に悪意があって設計しているとは限りません。なぜ、企業は意図せずにこのようなUI設計をしてしまうかを紐解きます。
オックスフォードアカデミックの論文「Shining a Light on Dark Patterns」では、ダークパターンが消費者の意思決定に与える影響を実証的に示し、法的に規制すべき根拠を提示しています。この論文では、ダークパターンが急増している理由として、A/Bテストで利益が最大化されることが明らかになったためであると述べられていました※12。
企業のデジタル施策では、CVRや会員登録率といった短期KPIの達成が強く求められ、指標を達成できるようなUI設計をします。そこでKPIを最適化すると、A/Bテストで出た結果をもとにした誘導的なUI=ダークパターンに陥ってしまうケースがあるということです。
つまり、テストの数値が良いものが正しいと判断されるため、ユーザー体験の質よりも数値が優先される構造的バイアスが生まれ、その結果、購入率を上げる工夫をしたつもりで、“残り3点”、“今だけ割引”などの煽るような文言が入ったものを採用してしまいます。しかし、ユーザーの視点では、「操作を誘導された」「選択肢が隠されていた」と感じ、ダークパターンとみなされているのです。
この方法で一時的にKPIは改善できますが、長期的にはユーザーの信頼を損なうUI設計です。対策としては、A/Bテストの評価軸に、定性的指標や倫理的な視点のUXチェックを加えて回避することができます。
国内ではダークパターンの包括的な定義やガイドラインが未整備です。そのため、判断のばらつきやチェック体制の不整合が、意図せぬダークパターンを生み出しています。UI設計の現場では、画面上の限られた表示領域に実装した機能やマーケティングの短期的成果を最大化するための設計が、会員登録の強制や緊急性を煽る設計になっている場合があります。
その結果、「このケースは違法になるかどうか」の判断が曖昧になってしまい、ダークパターンが発生してしまうことがあります。また、その状態で法務部門がレビューしても、そうした巧妙なUI設計の問題点を見落としてしまった場合、景品表示法・特定商取引法などに抵触するリスクを排除しきれない可能性もあります。
このような部門間の連携不足に陥らないためには、部門ごとの役割を果たしながら連携して検証を行うことが重要です。マーケティング部門はユーザー獲得数、制作部門はUI/UX、法務部門は法的リスクの管理をしている部門のため、目的や評価軸が異なります。
まず、制作・マーケティング部門は、ユーザーに誤認や誤誘導を生むようなUIについて理解を深め、ダークパターンの発生を防ぎます。その上で、法務部門は、景品表示法・特定商取引法・消費者契約法などに該当する可能性がないかをチェックします。それぞれの部門が検証すべき箇所を見ながら連携することで、企業全体でリスク検証を抜け漏れなくおこなえます。
定量データだけでは、そのUIがユーザーにどのように受け止められているかを十分に把握することができません。CVRや登録数などの短期指標を基にデザインを判断したことで意図せずダークパターンに陥るケースもあります。A/Bテストで数字の良い案を選んでも、ユーザーは「誘導された」「騙された」と感じているかもしれません。成果が上がっているように見えても、実際にはユーザー体験が損なわれている可能性があるのです。
このようなズレが放置されるのは、ユーザーの声を吸い上げる仕組みがないことが原因です。ユーザーインタビューや苦情の分析といった定性的なデータを評価プロセスに取り入れられれば、企業は自分たちとユーザーとの認識のギャップに気づけます。定期的にユーザーの声を集めて反映する体制を整えることで、数字に偏らないUI改善が可能になり、ユーザーとの信頼関係を守りながらより良い体験を提供できるようになります。
ECサイトやアプリを使う際にユーザーが「騙された」「選択肢がわかりにくい」と感じれば、それだけでも企業の信頼は損なわれてしまいます。ダークパターン対策は信頼を積み重ねるための第一歩であり、現代のUXには誠実さが求められる時代になったということです。
前述のように、日本では既存の法律を活用し、表示義務違反や景品表示法などに違反するとして措置命令を出すにとどまり、デジタル市場の健全性や消費者の保護のために消費者庁による実態調査やガイドライン整備を進めている段階です。しかしながら、現段階ではサイト運営に携わっている企業側がUI設計をする際、料金や解約方法を明確に表示する、チェックボックスは未選択を初期設定にするなど、ユーザーにとって透明性・選択の自由・納得感を軸に設計することを心掛けなければなりません。
ユーザーの意図しない誘導を防ぐには、デザイナーやディレクターの個々のリテラシーを高めることも大切です。しかし、企業としてのガイドライン整備や法務・コンプライアンス部門との連携、外部UI/UX監査の導入などでチェック体制や第三者の視点を取り入れる体制を構築し、確実にダークパターンを防ぐ必要があります。
他にも、苦情や解約理由、カスタマーサポートに寄せられる問い合わせ内容などを定期的にチーム内で共有・可視化する機会を持つのも有効です。UI/UXの改善にユーザーの声を届ける場を設けることで、設計者が気づきにくい意図しない誘導の兆候を汲み取り、設計改善に活かすことがダークパターンの予防につながります。
企業にとってダークパターンを含んだデザイン設計は、信頼を失いかねない明確なリスク要因です。解説した事例について、UI/UX設計に携わる企業のデザイナーやディレクターが認識を深めるのはもちろんですが、リーダー層が率先してこの課題に向き合うことがユーザー体験と企業価値の向上につながります。
顧客との信頼関係を築くことが何よりも強力なマーケティング施策であるということを改めて念頭に置き、長期的信頼とユーザー体験を評価軸に自社サイトのUXを見直し、誠実なUX設計へ転換しながら競争力に差をつけていくことが大切です。
当社では、UXリサーチやユーザビリティテスト、UXデザインの実装支援を通じて、顧客起点でのサービス開発や改善をサポートしています。また現場で継続的に改善を回す内製化支援もおこなっており、表層的なUI改善にとどまらない、体験価値中心のプロダクト設計やサービス成長をご支援しています。関心をお持ちの方は、下記サービスページより詳細をご覧ください。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。