執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
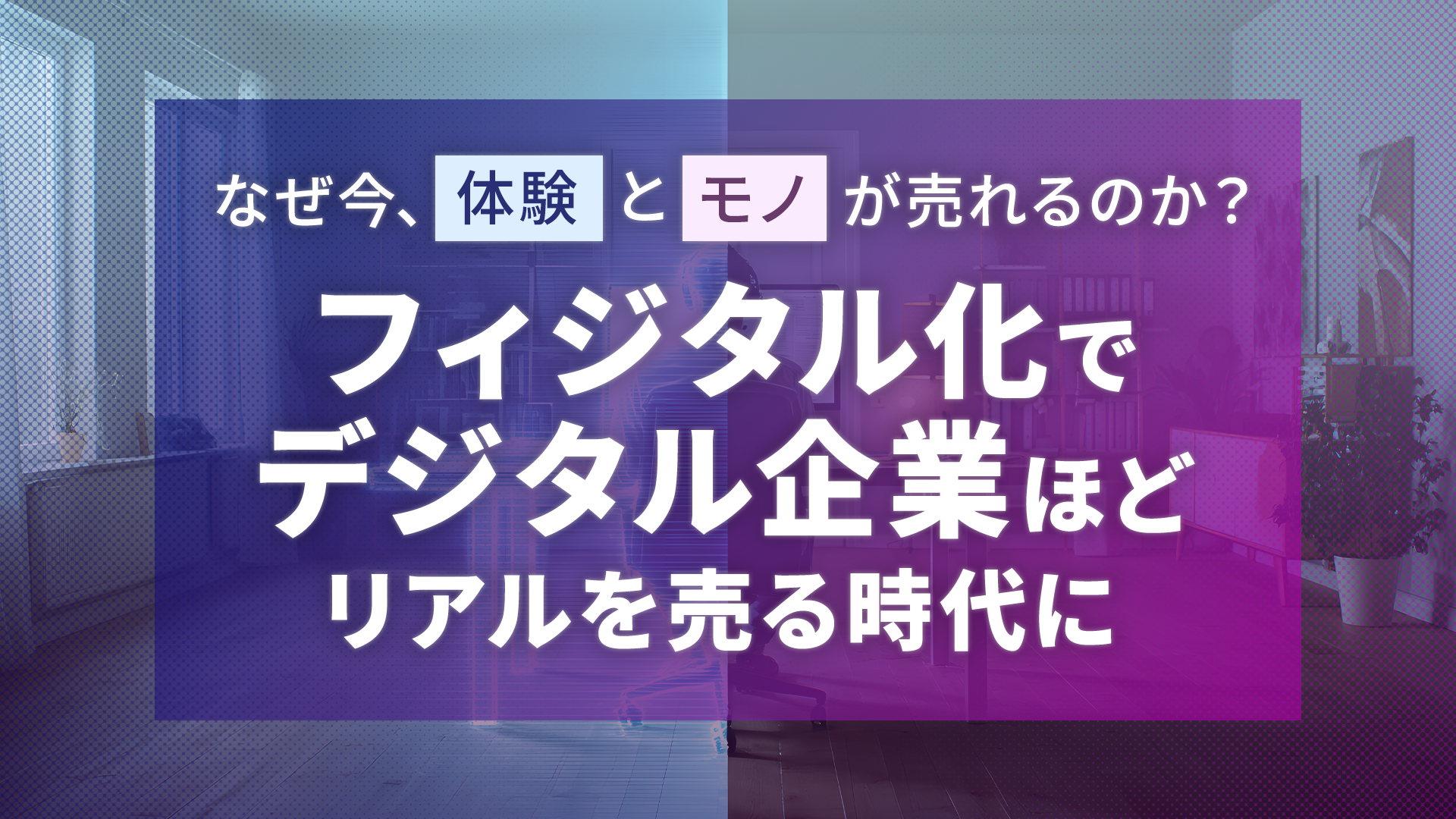

サブスクリプションや広告といった、かつて成長を牽引したデジタル収益モデルは、近年その勢いに陰りが見え始めています。広告単価の下落やユーザーの「サブスク疲れ」、そして生成AIが引き起こすコンテンツのコモディティ化。こうした状況のなかで、注目を集めているのが「フィジカル=リアル」な価値への回帰です。デジタル経済の限界と、リアルがなぜ再評価されているのか──その背景を整理します。
動画配信やSNS、サブスクリプション型のサービスが急速に普及したことで、デジタル企業はかつて、スケーラブルで高収益なモデルを手に入れたように見えました。コンテンツを蓄積し、配信し、アルゴリズムで最適化する。こうした、仕組み化された成長は、デジタル時代を象徴するビジネス手法でした。
しかし今、その成長は多くの領域で鈍化の兆しを見せています。広告単価の下落、ユーザー獲得コストの上昇、サブスクの解約率増加といった要因が重なり、「デジタルモデルだけでは持続的な収益成長は難しい」という構造的な課題が浮かび上がっています。
Deloitteの調査によれば、米国の消費者の約半数が複数のサブスクリプション管理や費用負担に「疲れを感じている」と回答。また、41%が「現在のサブスクは価格に見合っていない」と答え、前年より5ポイント上昇。さらに47%のユーザーが「現在支払っているストリーミング費用は過剰」と感じており、コストと感じる価値の間にギャップが生まれている実態が明らかになっています。
生成AIの進化により、テキストや画像、映像などのコンテンツ生成コストは大きく低下しました。誰もが短時間でコンテンツを生成できるようになり、情報の独自性や希少性に対する感覚も変わりつつあります。複製可能なものがあふれるなかで、唯一性やリアルな体験の価値が、相対的に高まり始めています。
こうした変化について、Deloitteは「コンテンツ制作の民主化」と表現しつつ、「誰でも作れるようになったからこそ、差別化された価値の創出が難しくなっている」と警鐘を鳴らします。つまり、コピーが無限にできる時代において、本物や唯一無二の意味が再定義されつつあるのです。
そのような環境下で、企業にとってはサブスク疲れやアルゴリズム依存から脱却し、「体験と共感」を軸に信頼と収益を生み出す新たな戦略──すなわちフィジタルが、次の成長の鍵として注目されつつあります。
リアルならではの価値が再び注目されるなか、新たな価値創出のキーワードが「フィジタル(Phygital)」です。VTuberなどデジタル発のIPが、リアルイベントや限定グッズを通じて熱量あるファン経済圏を築くなど、デジタルとリアルを融合した新たな収益モデルが広がりつつあります。ここでは、その定義と価値の本質を整理します。
「フィジタル(Phygital)」とは、「Physical(物理)」と「Digital(デジタル)」を組み合わせた造語であり、リアルとデジタルを融合した体験や価値提供を指します。2010年代初頭から小売・マーケティング業界を中心に注目されてきたこの概念は、近年その対象をIPビジネスやサブカルチャー領域にまで広げています。
一見すると、従来のO2O(Online to Offline)とも似ていますが、その違いは設計思想にあります。フィジタルは、オンラインとオフラインが互いに補完し合いながら、一貫したユーザー体験と収益性を両立する構造が特徴です。
DXは当初、業務効率化や構造改革を主眼に語られることが多かったものの、近年ではその文脈も広がり、体験価値を軸にしたアプローチが注目されるようになっています。そうした流れのなかで、デジタルとリアルを有機的に接続し、顧客の熱量を収益へと変換する「フィジタル」は、DXの深化系として位置づけられる取り組みといえるでしょう。
たとえばVTuber事業では、デジタル起点で形成されたファン基盤を、リアルイベントやグッズ販売といったフィジカルな施策で拡張。デジタルとリアルの接点を循環させながら、熱量の高いコミュニティと継続的な収益構造を実現しています。
こうした動きは、特にIPビジネスやファンコミュニティを持つ業態で顕著です。フィジタルが単なる演出ではなく、事業成長の戦略的柱として機能するケースも見られます。すべての企業に当てはまるわけではないものの、熱量を活かした中長期的な関係構築を目指す上で、有効な手段となり得るでしょう。
デジタルからリアルへ。この構造転換を、すでに収益モデルとして定着させている企業も存在します。ここでは、VTuber事業を展開するANYCOLORを中心に、音楽、映像、飲料、IPビジネスなど、さまざまな領域で「フィジタル化」が収益の柱となっている事例を紹介します。
ANYCOLORは、VTuber「にじさんじ」を中心としたIPを展開する企業と見られていますが、実際の収益の中核は、デジタル配信ではなく、グッズ販売やイベント体験を含むフィジタル領域にあります。2025年4月期には、フィジタル領域だけで年間376億円超を創出しており、その規模はYouTubeなどによる認知形成を担う配信収益を大きく上回っています。
具体的には、170名のVTuberを起点に、年間190件以上の周年記念品や限定グッズ施策を展開。さらにライブや展示会といった没入型イベントへと連動させ、「配信 → グッズ/イベント → 企業タイアップ」という多層的な導線を整備しています。ファンの熱量を段階的に育成・収益化するこのモデルは、まさにフィジタル戦略の先進事例といえるでしょう。
取り組み:アーティストの公式グッズを販売する「Spotify Shop」を展開しています。配信ページから直接購入ページへと誘導し、サブスクリプション以外の収益源を構築しています。
効果:Spotify全体の業績として、2025年Q2決算では、加入者数が前年比 +12% 増の2.76億人、月間アクティブユーザー(MAU)は同+11% で6.96億人に達したと報告されています。こうした規模拡大が、Spotify Shop の導線設計を支える土壌となっています。リスニングデータを活用した個別グッズ設計により、ファン体験と所有体験を滑らかにつなぐ導線が見られ、デジタルとフィジカルを循環させるフィジタル構造を支えるエコシステムと言えるでしょう。
取り組み:ゲームやアニメから派生したカードゲーム、グッズ、イベントなどを組み合わせ、フィジカルな経済圏を拡大しています。「希少性」や「所有欲」を起点に、熱狂的なファン層を形成しています。
効果:2025年2月期には売上高が4,109億円に達し、カードゲームは累計750億枚以上を出荷しています。フィジカル資産が中核収益として機能しています。
取り組み:F1やエクストリームスポーツなどのリアル体験を軸に、Red Bull Media Houseを通じたデジタル配信を組み合わせています。体験から共有、拡散へとつながるサイクルを設計しています。
効果:2024年には世界で126.7億缶の飲料を販売し、グループ全体の売上高は112.27億ユーロに達しました(前年比6.4%増)。この巨大な消費基盤を背景に、体験中心のマーケティング戦略がブランド熱量を醸成し、単なる飲料販売を超えた価値循環モデルを支えています。
取り組み:多くの人気クリエイターは、広告収益に加えて、グッズ販売、ライブイベント、会員制メンバーシップ、ファンミーティングといったリアル接点を拡張する動きを進めています。
効果:YouTube 自体の発表によれば、YouTube パートナープログラムに参加するチャンネルのうち、2024年には 5桁ドル以上の収益を上げたチャンネルの過半数が、広告以外の収益源(グッズ販売、メンバーシップ、ファン支援など)も併用しているというデータがあります。デジタルで高めた熱量をリアルな出会いや所有体験に収束させる構造が、徐々にモデル化されつつあります。
こうした事例に共通して見えてくるのが、フィジタル戦略が生み出す3つの価値軸です。フィジタルの本質は、リアルとデジタルの融合を通じて「新しい価値の創造」にあります。
デジタルとリアルの融合を、単発の施策で終わらせず持続可能な収益モデルへと育てるためには、戦略的な設計と着実な実行が欠かせません。本節では、中長期視点での設計プロセスと、短期的に取り組める具体アクションの双方を整理します。
顧客接点やIPの価値を中長期で高めていくには、段階的な実装と検証が求められます。ここで紹介するのは、フィジタルを一過性の話題ではなく、事業の柱として組み込むためのステップです。
加えて、フィジタルの実装では、「誰が、何を語るか」という起点の設計が重要です。熱狂的なファンを生むIPやブランドには、共感を喚起する物語や唯一無二の体験が伴います。逆に、熱量のないままリアル展開に踏み出すと、手段が目的化し、定着しないリスクも生まれます。まずは、既存のデジタル資産やコンテンツのなかに、「語られやすい物語」や「共感を呼ぶ強み」がどこにあるかを見極めることが、フィジタル戦略の出発点になるのです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| STEP1 | デジタル資産の棚卸と強みの再定義 | SNS・YouTube・配信コンテンツなど、すでに持っている資産を洗い出し、どの接点がリアル展開と親和性があるかを見極める |
| STEP2 | フィジカル展開モデルの構築 | グッズ販売、リアルイベント、企業コラボなど、顧客の「参加」や「所有欲」を刺激する設計をおこなう |
| STEP3 | 試験導入とKPI設計 | 小規模なトライアルでLTV・参加率・満足度などを定量的に検証し、段階的に拡張していく |
フィジタル戦略は、いきなり大規模に展開する必要はありません。既存の資産を活用して「何が顧客の心に響くのか」を低リスクで検証します。
| アクション | 内容 | ポイント |
| ACTION1 | コミュニティの「物理的接点」をつくる | オフ会、ファンミーティング、展示会など、少人数でも実施できるリアルイベントから始めてみる |
| ACTION2 | 希少性を演出したグッズ・体験を企画 | 限定アイテムや先行販売、抽選制のイベントなど、「今しか手に入らない」価値を付加する |
| ACTION3 | オンラインとリアルを連動させた体験ループをつくる | オンラインで参加したファンにリアル特典を付与したり、リアルイベントの余韻をオンラインで共有したりと、行き来できる体験設計を意識する |
リアルとデジタルを分断せず、顧客体験として一貫性を持たせる視点こそが、フィジタル戦略を左右します。まずは小さなトライアルから好循環の兆しを見つけ、それを育てながらスケーラブルな収益構造へとつなげていくことが、企業にとっての重要な次の一手です。
AIが無限のデジタルコンテンツを生む海のなかで、業務効率化を主眼としたDXだけでは、もはや顧客の心を掴み続けることはできません。これからの企業に問われるのは、デジタルとリアルを横断する一貫した「体験」をいかに設計し、顧客との永続的な関係を築けるかです。
その核心を担う一つがフィジタル戦略ですが、これを単発のイベントやグッズ販売といった「戦術」と捉えては本質を見誤ります。フィジタルとは、顧客とのあらゆる接点を「忘れられない体験」として捉え直し、事業全体を再設計するための新しい「OS(オペレーティングシステム)」といえます。
このOSを実装するために、先進的な企業はすでに次のような問いに向き合っています。
フィジタルへの最適化とは、単にリアルな施策を増やすことではなく、顧客を単なる「消費者」から熱狂的な「ファン」へ、そしてブランドとともに未来を創る「共犯者」へと引き上げるための、壮大な思想の転換といえるでしょう。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。