執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
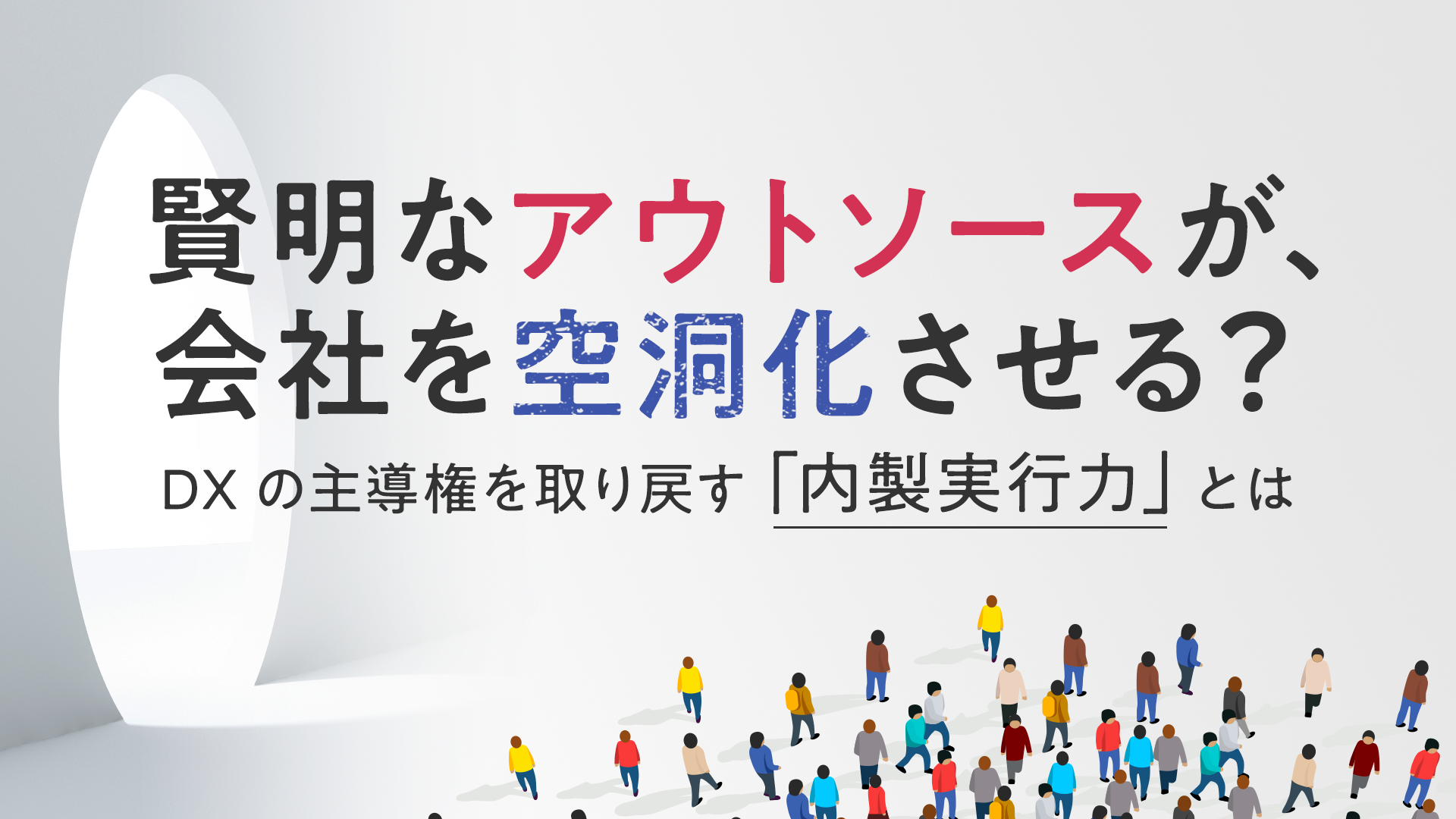

DXを外部委託で一気に進める──それはX社にとって、選択肢のなかでもっとも合理的に見えた道でした。しかし、その後に待っていたのは、誰も仕様を理解できない、誰も直せない、何も変えられない。そんな静かな崩壊のはじまりでした。
X社は、従業員3,000人を抱える老舗製造業。長年の非効率に悩むなか、「デジタルで生き残る」方針を掲げ、2015年に大手SIerのY社と包括的なアウトソース契約を締結しました。DX推進室が新設され、Y社の出向メンバーが中心となってプロジェクトが動き出します。しかし、社内のエンジニアがそこに関与することはありませんでした。
「専門家に任せればいい」──当時の社長は、社内報でそう語り、社内には期待と安堵が広がっていきます。初年度、CRMやERPなどの導入が一気に進み、売上は10%増。全社報告会では、DX推進室が壇上で表彰され、拍手が鳴り響きました。
当時、若手の1人はこう思いました。
「これがDXってやつか」
しかし、その拍手のなかには「自分たちは関係ない」という他人事感が混じっていたのです。
2018年──プロジェクトは順調に見えました。成果は出ていたし、トラブルも目立たない。Y社に任せておけば大丈夫。社内ではそんな空気が当たり前になっていきます。
DX推進室の業務は、ベンダーへの依頼と進捗の確認だけ。若手社員たちの間では、「この仕様は、なぜこうなっているんだろう」「そもそも、どこが課題だったんだっけ?」という疑問も出るようになっていましたが、会議では誰も口を開くことはありません。
Y社が書いた設計書はあったものの、その背景や意図を説明できる人は社内にいない。「余計なことは言わない方がいい」。そう言われて、疑問を飲み込んだ社員もいました。「コア業務に関係ないことは考えなくていい」。その無言の同調圧力が、静かに現場を覆っていたのです。
そんなある日、1通のメールが届きました。件名は、「体制変更に伴う支援終了のご相談」。Y社の担当が、事業再編を理由にプロジェクトから撤退するという示唆です。具体的な引き継ぎ期間も設けられず、社内に後任になるようなリーダーもいない。あまりにも一方的な宣告でした。
残されたのは、10年分の設計書と、誰も触れたことのないコードの山。X社の現場には沈黙が流れます。
「なぜ、この設計になったのか」
「どこをどうすれば、動くのか」
誰も答えられません。手がかりはあるはずなのに、触ることさえできない。「仕様を理解する」という当たり前のことを、いつの間にか現場メンバーは外に預けていました。
現社長──創業家の息子が、硬い声で漏らした言葉が、重い空気のなかに響きました。
我々は、資産ではなく、“負の遺産”を積み上げていたのかもしれない……
X社の10年の軌跡は決して他人事ではありません。成果が見える段階でDXを外注中心で進める企業は多く、外部パートナーに頼れば短期間で効率が上がるように見えます。しかし、短期的な成果と引き換えに、実装力や判断力といった無形の資産が社内に残らないという損失を伴っています。
ここでは、アウトソース依存が生む「組織の空洞化」のリスクを、4つの観点から整理します。これらの問題はX社の物語のなかに既に伏線として存在しており、多くの企業にも当てはまるものです。
X社のDXプロジェクトでは、立ち上げ当初からシステムの設計・開発をすべて外部ベンダーに依頼していました。成果こそ出ていたものの、その裏側で、「なぜこの設計にしたのか」「どう改善するのか」といった技術的な判断の背景は、社内に一切共有されないままでした。しだいに、現場は「よくわからないけれど、これが仕様らしい」という空気に支配されていきます。経営とIT部門の距離も広がり、戦略とシステムが別々の方向を向く。そんなブラックボックス化が進んでいったのです。
実際、メンバーズの「攻めのDX実態調査2025」によれば、9割超の企業がDX実行工程における人材不足を認識しており、約5割は「大幅に不足」と回答しています※1。特に求められているのは、技術理解やアジャイル実行力、効果測定力など、まさに“実装する力”です。
IPA「DX動向2025」でも、ビジネスアーキテクトやデータサイエンティストの不足が継続的課題とされ、設計思想や全体アーキテクチャの把握が困難になっている状況が示されています※2。自社に技術と判断の蓄積がなければ、システムが稼働しても、企業として「なぜこの形なのか」を説明できない。それは、将来にわたって選択肢を持たないというリスクを意味するのです。
プロジェクトが順調に進んでいるように見えたX社では、徐々にシステムの改修や追加開発のたびに、社内の誰もがベンダーに「お伺いを立てる」ようになっていました。自社にはコードも設計も読める人材がおらず、技術的な判断はすべて外注先に依存。小さな修正一つにも、見積もり→契約→調整といった重い手続きが必要になり、現場の施策スピードと経営の判断速度は乖離していきました。
このような構造的な硬直は、X社に限った話ではありません。三菱総合研究所の「DX推進状況調査【2025年度速報版】」によれば、「データ分析スキルを持つ人材不足」は年々解消傾向にある一方で、「ビジネス課題とデータ分析を結びつけて、具体的な施策に落とし込める人材」の不足がむしろ増加しています。
社内にあるべき判断力が外部に偏重し、改修のたびに多大なコストと時間がかかる。その結果、変化の早いビジネス環境に追いつけなくなっていく。これも、アウトソース依存が生む典型的なリスクです。
X社でシステムを管理していた現場社員が異動したとき、残されたのは形式的なドキュメントだけでした。「なぜこう設計されているのか」「なにを前提として動いているのか」──それらを説明できる人材は、すでに社内には存在しなかったのです。
このような断絶は、ベンダー依存によって技術や判断の蓄積が社外に偏っていたことの帰結でした。属人的な知識が引き継がれず、プロジェクトメンバーが抜けるたびに「一からやり直し」が必要になる。現場ではその非効率性に気づきつつも、対策を打つ時間も余力もないまま、次のプロジェクトが始まっていくのです。
レバテックの「IT人材白書2025」によると、DX人材の不足を「深刻」とする企業は6割を超えています。その背景には、ナレッジを継承し育てていく仕組みそのものが整っていないという課題があり、ノウハウが社外にしか存在しない構造的問題を多くの企業が抱えていることが示されています※4。
属人化、断絶、空洞化──。これらが重なったとき、組織は変化への対応力を大きく損ないます。そしてそのツケは、いずれ「動けない組織」となって現れるのです。
「それはベンダーが決めたことだから」「技術的に難しいと言われたので」──本来、経営層が意思決定すべき局面で、現場からこんな言葉が返ってくる状況は、すでに危険信号です。
DXは経営の戦略判断から生まれるケースも多い一方で、現場が試行錯誤を重ねながら気づきと改善を積み重ねることもまた、変革の源泉です。しかし、その現場の判断が外部の制約に縛られてしまえば、たとえ経営が旗を振っても、企業全体としての自律的な変化は実現できません。
Gartner Japanの「DX意思決定実態調査2025」によれば、国内企業の約7割が「DXを推進中」と回答する一方で、IT部門の62%が「既存業務の維持・改善」に注力しているという実態が浮かび上がっています※5。これは、現場の創意工夫や挑戦が守りに傾いていることを示唆しており、変化を起こすエネルギーが、仕組みのなかで封じられている状態といえるでしょう。
X社でも、ベンダーからの「この仕様が限界です」「これは無理ですね」という一言が、事実上の経営判断になっていました。経営が未来を描こうとしても、現場が動けず、ITが外部に握られている限り、変革は進みません。経営と現場が一体となり、主体的に判断し、行動できる状態こそが、持続的なDXの土台なのです。
「外注か、内製か」という二項対立ではなく、いま企業に求められているのは、自ら構想し、試し、変えていける実行力のある内製体制です。メンバーズ「攻めのDX実態調査2025」によれば、内製化が進む企業ほど「アジャイル開発力」や「顧客中心設計」の実行に課題を抱えていることが分かっています※6。X社が直面したように、内製実行力が備わらないままDXを進めた先には、「設計された仕組みを運用するだけ」の硬直化が待っています。内製実行力の本質と、それを資産化するための条件を見ていきましょう。
変化の激しい時代において、内製チームの最大の強みはスピードと柔軟性です。ビジネス現場と密に連携しながら、仮説を立て、即座に実装・検証するサイクルを回せること。それにより、意思決定の精度や再現性も高まり、経営と現場が連動するDX実行基盤が生まれます。「施策の効果検証ができない」「改善サイクルが回らない」という課題は、内製実行力の欠如が原因であることも多いのです。
内製化とは、すべての工程を自社だけでおこなうことではありません。外注を活用する場面も多くありますが、重要なのは「判断」と「改善」の主導権を自社が持ち続けることです。例えば、設計思想や技術選定の背景を理解し、仕様の意図を語れる人材が社内にいること。それが、外部パートナーとの対等な関係を築く上でも不可欠です。主導権を持てない状態では、内製化もアウトソースも機能しません。
内製実行力が真に企業の資産となるには、単なる開発力にとどまらず、現場知の継承と進化の仕組みが必要です。ナレッジや改善事例が記録・共有され、次のチームや世代がそれを活用できるようになったとき、企業は「学習する組織」としての成長サイクルを手に入れます。さらに、伴走型の支援パートナーとともに現場の課題を乗り越えていくことで、外部と連携しながらも、自社に知識と判断基準を残す文化が醸成されます。
X社のように、内製実行力が育たないまま外注に依存すれば、ノウハウの蓄積は進まず、変化に柔軟に対応する力も失われます。逆に言えば、内製化によって現場に知識が残り、次世代を育てる構造を持てれば、それこそが持続可能なDXの基盤になるのです。

アウトソースの活用は、DX推進の初期段階では即効性のある手段となり得ます。しかし長期的な視点では、「ノウハウの蓄積」や「変革への支援」といった観点で課題が残ることも明らかになっています。メンバーズ「攻めのDX実態調査2025」によれば、外部委託で満足度が高いのは「常駐など密なコミュニケーション」(44.9%)である一方、「ノウハウ蓄積」や「変革支援」は2割台にとどまっています※7。
では、こうした構造的な課題を乗り越えるために、企業はどこから「内製化の一歩」を踏み出せばよいのでしょうか。脱・アウトソースに向けた具体的なステップを4つの視点で紹介します。
大きな構造改革よりも、まずは小さな成功体験から始めることが、内製推進の現実的な第一歩です。たとえば、社内で困っている業務やUIの改善など、明確な課題を3〜5名の小規模チームで取り組む。仮説を立て、すぐに試し、成果を出す──そのサイクルを回すことで、現場の実行力が育まれます。小さな成功は、周囲を巻き込む説得材料にもなります。こうしたスモールスクラムが、内製文化の発火点となるのです。
内製の推進において、要となるのは「現場に寄り添いながら、ビジネスと技術を橋渡しできる人材」です。専門スキルだけでなく、社内の文脈やユーザー視点を理解し、チームを導けるリーダーの存在が不可欠です。このリーダーは、プロジェクトを前に進めるだけでなく、内製という文化を社内に根付かせていく役割も担います。明確に選出し、裁量と支援を与えることが、内製推進のスピードを決定づけます。
単なる「作業委託」ではなく、知識移転を前提とした契約設計への転換が求められます。たとえば、OJTの仕組みを整備したり、準委任契約に切り替えたりすることで、外注先から得られる知見を自社に残すことが可能になります。また、ベンダーを単なる外部労働力とするのではなく、現場支援、伴走支援パートナーとして捉えることが、長期的な内製力の育成につながります。
技術や体制だけでは、内製化は根づきません。必要なのは、失敗を許容し、学びとして共有できる文化づくりです。ナレッジの積極的な発信、再利用、改善が組織全体で奨励される環境が重要です。さらに、評価制度も内製実行力に即したものへと見直す必要があります。チーム成果や改善活動へのインセンティブ設計をおこなうことで、内製文化を継続的に支える土壌が整います。
X社の10年は、短期的な効率性を優先し、外部パートナーにシステム開発・運用を依存した結果、事業の根幹である「判断力」までをも外注化してしまった典型例です。その結果、10年後に残されたのは、事業継続性を脅かすブラックボックス化したシステム、すなわち「技術的負債」でした。
DXは、単なるIT導入や業務効率化ではなく、企業の意思決定構造そのものを問い直す取り組みです。だからこそ、「内製実行力」とはコードを書く能力ではなく、現場が自ら問い、実行し、改善する力──すなわち企業の自律性に他なりません。
内製化の本質は、組織の内向き志向ではなく、現場と経営をつなぎ直し、学びと挑戦を繰り返す土壌を育てることにあります。そのためには、現場の知識や経験を尊重し、再び自社の組織能力向上に貢献してくれる戦略的実行パートナーを選ぶことが不可欠です。
これらの問いに明確に答えられたうえで、DXの主導権を自社の手に取り戻すこと。それが10年後の持続的な成長を実現する唯一の道です。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。