執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
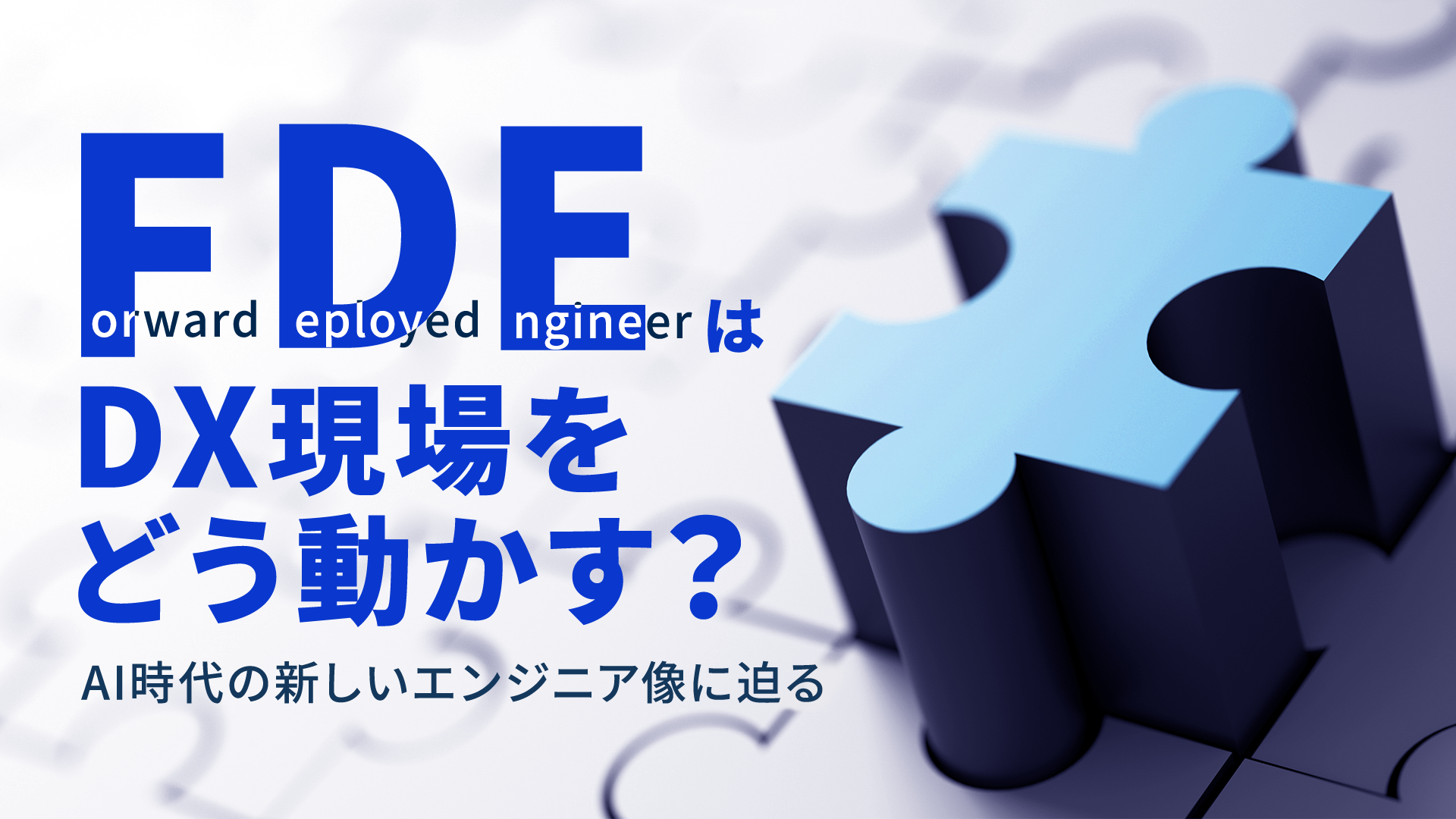
日本企業でもAIやデジタル技術の導入は急速に進んでいます。しかしその一方で、成果につながらない導入が相次いでいます。PoC止まり、現場での活用が進まない、ROIが見えない──。表面的な導入は進んでいるにもかかわらず、肝心の「業務改革」や「競争力強化」に直結していないのです。IPA(情報処理推進機構)の「DX動向2024」でも、AIやデジタル施策の導入が進む一方で、業務改革や成果創出には十分結びついていないことが国内企業の大きな課題だと指摘されています※1。
AI導入が期待された成果に結びつかない背景には、単純な技術不足以上に、現場への浸透を妨げる構造的な要因があります。特に企業の現場で繰り返し顕在化しているのが、次の3つの壁です。
技術の壁
多くのAIツールは単体で完結せず、既存の基幹システムや業務フローとの連携が必要です。しかし、連携が複雑だったり、カスタマイズの負担が大きかったりすると、現場にとっては別物の仕組みに見えてしまいます。その結果、せっかく導入しても業務に組み込めないまま活用が進みません。
業務の壁
AIが提供する新しい操作やプロセスが、日常のオペレーションに馴染まないこともあります。現場から見ると「余計な作業が増えた」と映りやすく、利用が広がらないまま立ち消えてしまうのです。実際に「使いこなせない」「従来のやり方のほうが早い」といった声が上がるケースも少なくありません。
組織の壁
さらに厄介なのが組織的な抵抗です。IT部門と業務部門の間にはしばしば温度差があり、変革は必要と頭では理解していても、現場では、今のままで十分と考える人も多いのが実情です。この心理的ハードルが、導入したAIを日々の業務に定着させる妨げになります。
これらの壁は単独でも障害となりますが、往々にして複合的に作用し、導入の効果が大きく損なわれます。結果として、AIは「導入したはずなのに成果が見えない」存在となり、経営層や現場双方の失望を招いてしまうのです。
ベンダーは導入や納品までは対応できますが、現場での活用や改善にまで伴走することは難しいのが現実です。また、社内のDX推進担当も多忙で、個別現場に密着して改善サイクルを回す余裕がありません。その結果、欠け落ちてしまうのが「最後の1マイル」です。これはシステムやAIを導入した後に、現場が実際に使いこなし、継続的に改善し続けるまでのプロセスを指します。
IPAが2022年にまとめた調査報告※2でも、現場の主体性や運用改善サイクルを築けないことがDX失敗の要因とされており、この「最後の1マイル」の欠如こそが、AI導入が成果に結びつかない本質的な理由です。
では、この「成果なき導入」をどう乗り越えるのか。カギとなるのが、技術と現場をつなぐ役割を担う人材です。その具体的な解として、米国の先進企業で体系化され、日本でも注目が高まっているのが FDE です。
FDE(Forward Deployed Engineer)とは、顧客の現場に深く入り込み、技術と業務を橋渡しするエンジニアを指します。この職種が体系化されたのは2010年前後、米国のデータ分析企業 Palantir による「Forward Deployed Software Engineer(FDSE)」、通称 Delta に遡ります。Delta は単なるシステム導入担当ではなく、顧客の業務や課題を理解したうえでプラットフォームを最適化し、現場に定着させる役割を担いました。製品を「地上展開(deployment)」し、実際の業務で価値を発揮させる中核人材として位置づけられていたのです。
その後、この考え方は Scale AI や Anduril などのテック企業へ広がり、近年では OpenAI や Ramp といった AI・SaaS 企業での採用・活用も加速しています。FDEは、技術の提供にとどまらず、現場で成果を実現する推進者として進化を続けています。
FDEはソフトウェア開発だけでなく、顧客との密な協働やロードマップへの示唆、改善策の立案などにも関与します。マイクロソフトやUberで技術リーダーを歴任し、現在は著述家・コンサルタントとして活動する Gergely Orosz氏 は、この役割を次のように表現しています。
「FDEは、スタートアップのCTOのようにビジネス成果に直結する高リスク・高インパクトの案件を、少人数チームでエンドツーエンドに担う存在である。顧客課題を直接解決し、その成果は不良品削減といった具体的なビジネスKPIで評価される。FDEのミッションはビジネス成果に直結した価値創出。コンサルタント的に業務課題を解決する役割と、プラットフォームエンジニアとして技術を実装する役割、その両面を兼ね備えたハイブリッドな職種だ」
Orosz氏は Palantir の Delta(FDE)を中心に、Scale AI や Anduril などの事例を比較し、FDEが AI・データ活用の実務において急速に存在感を増していると整理します。※3
こうした潮流は日本企業にも波及しています。たとえば、SaaSとFintechを軸に事業を展開する LayerX では「AI・LLM Forward Deployed Engineer」という役割を掲げ、現場密着型でのAI活用を推進する人材を募集しています。海外発の概念であるFDEが、日本においても実務レベルで取り入れられつつあることを示す動きです。
FDE的アプローチは、従来の常駐型エンジニアの延長線上にありながら、より現場密着型に進化したモデルといえます。単に導入支援をおこなうだけでなく、実装から定着、さらには価値創出までを一貫して担う点に特徴があります。従来型常駐との比較を通し、進化の方向性を掘り下げていきます。
FDEの最大の特徴は、導入から成果創出までを一気通貫で担う点にあります。単にシステムを導入するだけではなく、現場で実際に活用され、成果に結びつくまでを見届ける姿勢こそが、従来型の支援とは大きく異なるところです。具体的には、次の3つの価値が挙げられます。
実装支援:顧客の環境や業務フローに合わせたソフトウェアのカスタマイズや統合をおこない、導入をスムーズに進める。
定着支援:単なる導入で終わらせず、現場に根付くまで伴走しながら業務プロセスを理解・改善し、日常のオペレーションに組み込める状態をつくる。
価値化支援:ROI(投資対効果)を意識し、導入した技術が生産性向上やコスト削減、新しい価値創出といった成果に結びつくよう、継続的に改善をおこなう。
こうした取り組みを通じて、FDEは技術理解と業務理解を兼ね備えた存在として、現場と製品開発の間にフィードバックループを築いていきます。これは従来の伴走型常駐エンジニアにも通じる特徴です。しかし、FDEはそのアプローチをさらに体系化し、成果創出までを強く意識する点で一歩先を行きます。こうした進化形のモデルとして、いまFDEが注目されているのです。
上記のような背景から、FDEはAIやSaaSの導入が進む現代において戦略的な役割を担うようになっています。米Fintech SaaSユニコーンの Ramp 社の公式エンジニアリング発信媒体「Ramp Builders Blog」は、FDEは「B2B企業における戦略的資産」として、特に「顧客現場から直接学び、迅速に統合・カスタマイズできること」が競争力の源泉になる、と言及しています※4。これは米Tech業界におけるFDEの存在感の高まりを象徴する見解です。
さらに、この潮流は国内外の議論にも広がっています。米国のスタートアップアクセラレーター Y Combinator のメンバーは、Palantir に始まる FDE のロールに言及しつつ、「AI導入の成否は、現場に入り込み、業務を理解し、それをソフトウェアに落とし込むことにかかっている」と指摘しています。近年では「創業者自身がFDE的に動かなければ成功できない」という認識も広がっており、FDE的アプローチは単なる職種を超えて、スタートアップの経営実践そのものに浸透しつつあるのです。
国内でも、経営層や技術リーダーから「日本企業のAI定着にはFDE的役割が不可欠だ」といった声が出始めています。実務面での活用だけでなく、経営や組織戦略の文脈でもFDEの必要性が語られつつあり、AI導入の次のステージを象徴する動きといえるでしょう。
FDE的なアプローチの特徴は、従来型の客先常駐エンジニア像と比較することでより鮮明になります。従来は、依頼された作業を遂行する外部リソースとしての役割が中心でしたが、FDEは「現場に伴走しながら成果を共創する推進者」として設計されている点に違いがあります。
| 従来の客先常駐エンジニア | FDE的なアプローチ | |
| 役割 | 指示された作業を遂行する | 課題を発見し、解決まで推進する |
| 責任範囲 | 開発や運用など技術実装に限定 | 実装~定着~成果創出まで一貫して担う |
| スタンス | 受け身・指示待ち | 自走・提案・現場を巻き込み推進 |
| 成果指標 | 工数消化・納期遵守 | ビジネスKPIの達成・ROI改善 |
| スキルセット | 特定の技術スキル | 技術 × 業務理解 × 推進力 × コミュニケーション |
| 関与期間 | プロジェクト単位 | 中長期的に伴走し改善を継続 |
| 現場との関係性 | 外部リソースとして位置付けられる | 内製化を促すパートナーとして共創する |
この比較からもわかるように、従来のカスタマーエンジニアや常駐型人材が技術導入やサポートにとどまるのに対し、FDE的アプローチは業務プロセスや意思決定にまで踏み込み、持続的な価値創出にコミットする点が決定的な違いです。
AIやデジタル施策は導入することよりも、組織をどう変えるかが問われる段階に入っています。FDEは、現場人材を育て、部門をつなぎ、投資効果を高める触媒として機能していきます。現場に入り込み知識を移転するだけでなく、横断的な推進力を発揮して成果を積み上げるのです。こうした伴走を通じて、外部依存型の体制を「自ら進化できる組織」へと変えていきます。
FDEは、現場のエンジニアや担当者と並走し、知識やスキルを移転することで、人材の成長を後押しします。単なる外部リソースとして業務を肩代わりするのではなく、現場に根ざした協働を通じて、自走できる力を育てていくのです。
たとえば LayerX 社内での実践(AIワークフローの定着に向けた取り組み)では、FDEが現場業務を形式知化し、その知見をプロダクトに組み込むプロセスを通じて、メンバー自身が課題を発見し解決する力を高めていきました※5。FDEは「現場に入り込んで成果を出す」だけでなく、現場の自走力を育み、外部依存から「自ら改善し続けられる組織」への転換を促すのです。
FDEのもう一つの特徴は、部門横断で推進力を発揮する点にあります。IT部門に閉じず、業務部門や経営層とも連携しながら、全社的な合意形成と変革を後押しします。結果として、従来の組織構造にありがちな「サイロ化」が解消され、プロジェクトが横断的に進む基盤が整うのです。
Palantir の公式ブログでも、同社の FDE(「Delta」と呼ばれる役割)が「製品開発と顧客現場の橋渡し役」として紹介されています※6。Delta は現場の抵抗感を和らげつつ、変革に向けた一体感を醸成する存在であるとされており、まさに推進体制を強化する役割を担っていることがわかります。
さらに国内においても、「AIは裏方として大量処理・提案・分析などを担い、人間が最終判断や対顧客接点を伴走的に担う」というヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)型の考え方が浸透しつつあります。こうした枠組みの実践的な担い手として、FDE的な人材が技術と人をつなぐ接着剤の役割を果たす期待があります。
冒頭で触れたように、AIの導入では「PoCで止まる」「成果が見えない」といった失敗例が後を絶ちません。その多くは、導入した技術が現場に定着せず、十分に活用されないまま終わってしまうことに起因します。この課題をFDEはどう克服するのか。それは導入から定着、さらに価値創出までの一気通貫での支援です。投資回収のスピードを高め、継続的な成果を生み出すという期待があります。
ポーランド発のソフトウェア企業 10Clouds も、FDEを「単なる実装要員ではなく、導入した技術を現場で使いこなし、継続的に改善することでROIを高める存在」と位置づけています※7。成果を数字で示すことで経営層の意思決定を支え、次の投資へとつながる好循環が生まれます。
FDEは単なる技術支援者ではなく、組織に変化をもたらす触媒となる存在です。内製化の促進、部門横断の推進力強化、ROI改善という三重の効果を通じて、企業のAI導入を一過性の施策から持続的な進化へと導きます。
AI導入の最大の課題は、技術力そのものではありません。真に難しいのは「導入したAIが現場に根付かないこと」です。こうした課題に対し、FDEは導入から定着・価値化までを一貫して伴走し、この「最後の1マイル」を埋める存在として機能します。一気通貫で伴走する過程で外部依存から内製化へ、部分最適から全体最適へと企業をリード。現場を動かす推進パートナーとして、そして企業変革を加速させていきます。
ここで改めて問いたいのは、貴社のAI導入が本当に「現場で成果を出しているか」です。導入や、PoCの段階で立ち止まってはいないでしょうか。もし心当たりがあるなら、いまこそ「最後の1マイル」をどう埋めるかを検討すべきタイミングかもしれません。
では、次に取るべき一歩は何でしょうか。まずは自社の現状を棚卸しし、「最後の1マイル」を埋めるための支援が必要かどうかを確認することです。FDEは海外のテック企業で発展してきた新しいエンジニア像ですが、その本質は「顧客の業務変革をともに進める伴走型パートナー」である点にあります。
私たちメンバーズには、現場に入り込み、お客さまとともに成果を積み上げるエンジニアが多数在籍しています。私たちは自社プロダクトを持つわけではありませんが、だからこそ幅広いAIやデジタル施策の導入において、中立的な立場から定着と活用を支援できます。AI導入を「止めない」ために必要なのは、必ずしもFDEという肩書きを持つ人材ではありません。現場に密着し、伴走しながら成果創出を支えるエンジニアが、その役割を果たしていくのです。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。