執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
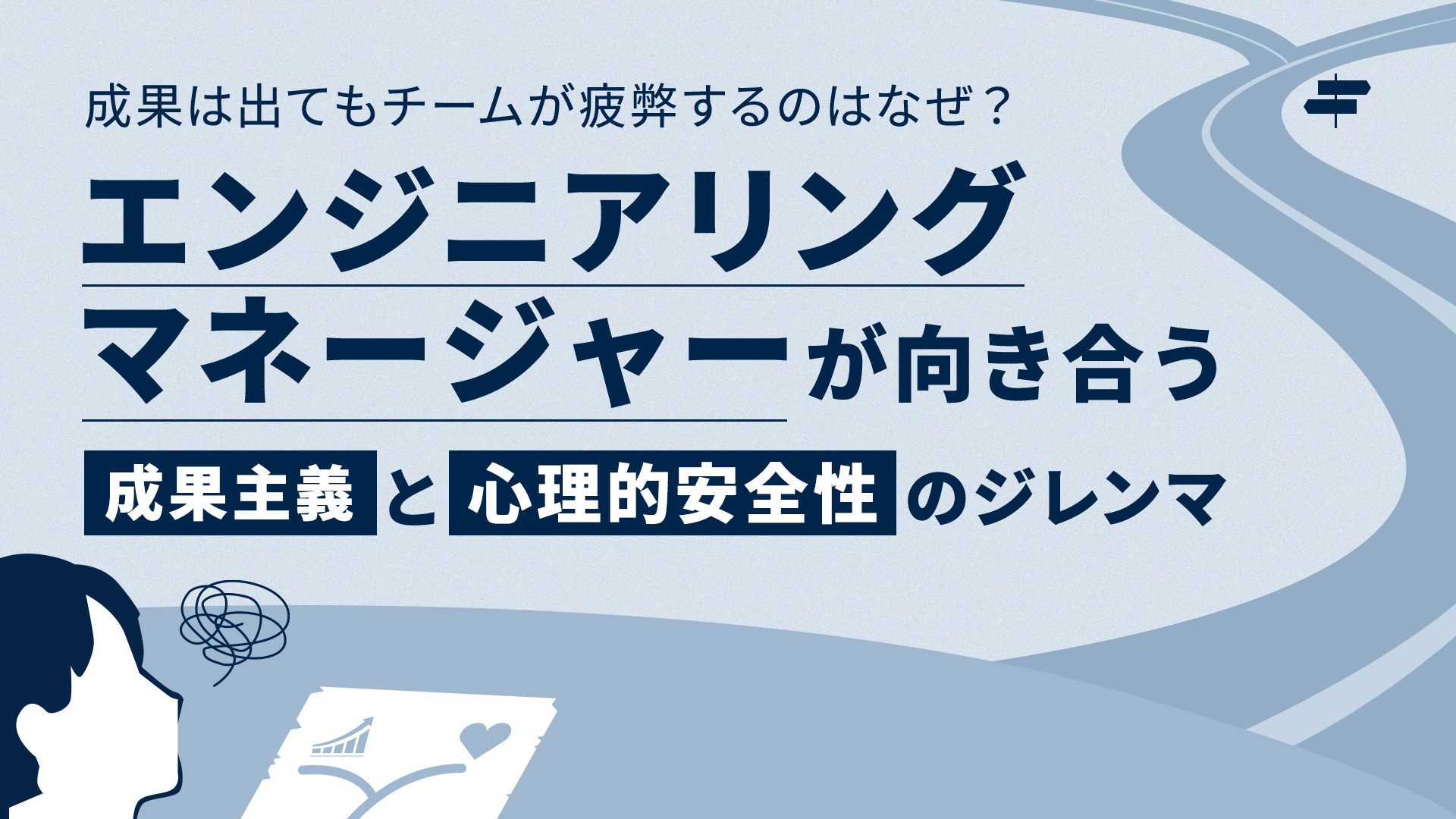
「今、まさに求められているのは、曖昧で不確実な状況でも意思決定し、進むべき道を示す力です」
そう語るのは、Microsoftのサティア・ナデラCEOです。生成AIがコードを書く時代となった現在、人間に必要なのは「誰よりも手を動かすこと」ではなく、「まだ見えていないものを捉え、関係性のなかから答えを導き出す力」だと強調しています※1。この言葉は、今まさに開発組織の現場で悩んでいる多くのエンジニアリングマネージャー(EM)にとって、大きな示唆を与えるものです。
「目標は達成しているのに、なぜかチームが疲弊している」「かつて優秀なエンジニアだった人が、マネージャーになった途端に評価が下がった」──そんな違和感が、いま各所で顕在化しています。こうした現象は、マネージャー個人の資質に帰結する話ではありません。背景には、生成AIやリモートワークにより可視化の対象が変わったこと、そして旧来の一律的な昇進ルートが今の現場にそぐわなくなっていることがあります。
成果を出すエンジニアが、必ずしもマネージャーに向いているとは限りません。それにもかかわらず、多くの組織では「優秀なエンジニア=EM候補」とみなされる構造が根強く残っています。その結果、評価基準や期待の中身が曖昧なまま任命され、本人もチームも徐々に疲弊していくのです。
EMとテックリード(TL)は、現場で混同されやすいロールのひとつです。両者が曖昧なまま運用されていると、意思決定や評価の軸がぶれ、組織に混乱をもたらす要因になります。
本来、EMとTLは序列ではなく、それぞれが異なる責任を担う補完関係にあります。TLは技術的な意思決定と品質のリードを担う存在であり、アーキテクチャや開発方針の方向づけが主な役割。一方でEMは、チームビルディングやキャリア支援、他部門との連携など、人とプロセスのマネジメントを担います。
オープンソースのキャリア開発フレームワーク「Engineering Ladders」は、TL=System、EM=Peopleと整理し、両者が協働することでチームの健全性と技術力が両立できるとしています。
優秀なエンジニアが昇進後に伸び悩むのは、本人の努力不足ではなく、「プレイヤー」と「マネージャー」に求められるスキルや貢献軸が根本的に異なるためかもしれません。両者の役割と評価基準の違いを明確に整理し、適材適所のキャリア設計をどう進めるかを考察します。
多くのIT企業では、かつて「成果を出したエンジニアはマネージャーに昇進する」という単線的なキャリア設計が一般的でした。しかし近年では、この構造を見直す動きが広がりつつあります。
たとえば、Rakus Partnersが2025年に実施した調査※3では、管理職に就いている人の半数以上が10年以上のエンジニア経験を有している一方で、比較的経験が浅い段階で昇進しているケースも一定数見られました。これにより、昇進に求められる資質として、専門性の高さだけでなく、リーダーシップ、採用戦略の理解、組織マネジメントの能力などが重視されていることが示唆されています。
プレイヤーとして高い専門性を発揮していたエンジニアが、マネジメント職に就いた途端に悩みを抱えたり、評価の低下に直面したりするケースは珍しくありません。これは、専門性とマネジメント適性を混同したまま昇進させる構造に原因があります。HR総研の調査※4では、ITエンジニアに対応した人事制度を導入している企業は16%にとどまる一方で、導入企業の96%は「マネジメントを免除されたスペシャリスト職」を設けており、専門性を軸としたキャリアが必要とされている現実が浮き彫りになっています。
SBテクノロジーでは、管理職ルートと並行して専門職として活躍できる制度を整備し、選んだ道によって評価や報酬に差が出ない仕組みを導入。どの貢献スタイルでも正当に評価される仕組みが、個人と組織の両方にとって健全な環境を支えています。エンジニアにとって昇進とは、マネージャーになることではなく、自分の強みを最大限に活かせるポジションを選べること。それを可能にする制度設計こそが、これからの組織に求められるのです。
プレイヤーとマネージャーでは役割が本質的に異なる以上、「昇進=マネージャー」という一律のキャリアルートにこだわる必要はありません。近年では、専門性を軸に昇進・報酬向上を可能にする「Individual Contributor(IC)トラック」を整備する企業も見られます。これは、エンジニアとして「コードを書く」「設計/アーキテクチャに影響を与える」「専門技術で組織に価値を提供する」ことを主軸とし、マネジメントを伴わずにキャリアを上げていく道筋を指します。
日本のSaaS企業RevCommでも、IC職とEM職を別トラックで評価・昇給する制度を導入しており、それぞれに適した評価指標を設定しています。こうした制度は、マネジメント適性にかかわらず、技術を極めたいプレイヤーにとって重要な選択肢となります。自身の強みや志向に応じたキャリアを選べる仕組みこそが、持続可能な人材活用の鍵なのです。
人材登用の基準として、しばしばマネジメント適性が問われます。しかし、これからの時代に必要なのは「この人はマネージャーに向いているか?」ではなく、「この人がもっとも力を発揮できるのはどの役割か?」という問いを起点にする視点です。
EMはキャリアの頂点ではなく、あくまで多様な貢献ルートのひとつです。プレイヤーが技術的な専門性を追求しながら、正当に評価される仕組みを整えること。そして、マネジメントに適性のある人材が、その役割に集中できる環境をつくること。それが、個の成長と組織の柔軟性を両立するカギになります。

成果主義に基づく評価は、個人のモチベーションや短期的な成果を引き出すうえで有効です。しかし、数値や成果にフォーカスした評価軸は、協働や創造性を阻害し、チームの持続的な成長を難しくする側面もあります。
特にEMの立場では、チーム成果の最大化と、メンバーが安心して力を発揮できる関係性づくりという、一見相反する課題の両立が求められます。そこで生じるジレンマにどう向き合うかが、マネジメントの質を左右します。ここでは成果主義の限界をふまえ、EMがチームの心理的安全性をどう育み、制度設計にどう組み込んでいくべきかを掘り下げます。
チームが成果を上げるためにもっとも重要なのは、優れたスキルや明確な目標ではなく、「安心して発言できる関係性」にある。Googleが2012年に実施した大規模調査「Project Aristotle」は、180以上のチームの分析を通じて、心理的安全性こそが高パフォーマンスを支える最大の要因であると結論づけました※5。
2025年に発表された研究でも、オープンソースプロジェクトにおける心理的安全性が、開発者の継続的な関与に直結することが示されています※6。Pull Request(PR)上でのコメント数やコミュニケーションから心理的安全性スコアを定量化すると、これが高いチームほど、1年後・5年後におけるコントリビューターの継続参加率が有意に高いという結果が得られました。意見を言っても安全だと思える関係性が、チームの成果を支えることが示されています。
「何を達成したか」だけでなく、「どう取り組んだか」も含めて評価する視点も、これからのEMには不可欠です。定量的な成果指標(例:タスク完遂率や目標達成度)に加え、レビュー対応や新人支援、ナレッジ共有といったチームへの貢献行動を評価軸として組み込む必要があります。
その際に有効なのが、360度評価やピアレビューといった、複数の視点からのフィードバックを活用した仕組みです。こうした設計により、成果だけでは見えにくい「信頼の構築」や「関係性への働きかけ」も可視化できるようになります。EMには、人やチームの貢献を適切に捉える目線と、それを制度に落とし込む設計力が求められるのです。
成果だけでなく、日々の気づきや学びを言語化・共有する文化をいかに育むか。これもEMの重要な役割のひとつです。定期的な1on1や振り返りの機会を設け、目標や課題、行動の背景についてメンバー同士がフィードバックを交わすことで、内省と対話のサイクルが組織に根づいていきます。
また、失敗を許容し、プロセスを称える空気づくりは、心理的安全性の土壌を耕すうえで不可欠です。EMは単なる管理者ではなく、健全な関係性と学習環境を設計するデザイナーとも言えます。チームが自律的に成長できる場を整えることこそ、EMが果たすべき中核的なミッションなのです。
成果と評価、適性と制度、チームと個人──本記事では、EMという役割を取り巻く構造的な課題を見てきました。いずれのテーマも、単純な解決策で済むものではなく、グレーな領域に向き合いながら、問い続ける姿勢が問われるものでした。EMに本当に求められているのは、「正解を出す力」ではなく、「問いを持ち続ける姿勢」とも言えます。成果主義や心理的安全性、技術と人材育成、キャリア分岐といった複雑なテーマに対し、唯一の解を示すのではなく、チームとともに考え、探求し続ける在り方こそが、現代のマネジメントに必要とされています。
実際、リーダーシップ研究の第一人者であるハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授も、「率直な質問」「謙虚な傾聴」「誤りの共有」といった姿勢が、成果と心理的安全性を両立させる鍵になると指摘しています※7。「問いかける力」は、個人と組織の変化を促すリーダーの資質として、いま再評価されているのです。
EMという役割にすべての人を当てはめるのではなく、それぞれの強みや志向に応じたキャリアの選択肢を制度として整備することが、これからの組織運営には欠かせません。たとえば、マネジメントに限らず、技術的専門性を軸にキャリアを伸ばせる道筋を明確にすることで、個人のモチベーションを損なわずに成長を支援できます。こうした仕組みは、無理な登用を避け、組織全体の柔軟性と持続性を高めるうえでも有効です。
あなたがEMであるなら、「いま、このチームに必要な問いは何か」「その問いがチームの成長を促すものか」を問い続ける姿勢こそが、信頼されるリーダーとしての土台となり、組織に変化をもたらす原動力になります。組織を設計する立場にあるなら、EMやTL、スペシャリストが互いに補完し合える柔軟なキャリアパスを整えていくことが求められます。問いを持ち続けるリーダーが育ち、支え合える環境を整えること。それが、変化の時代に持続可能な組織をつくるのです。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。