執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
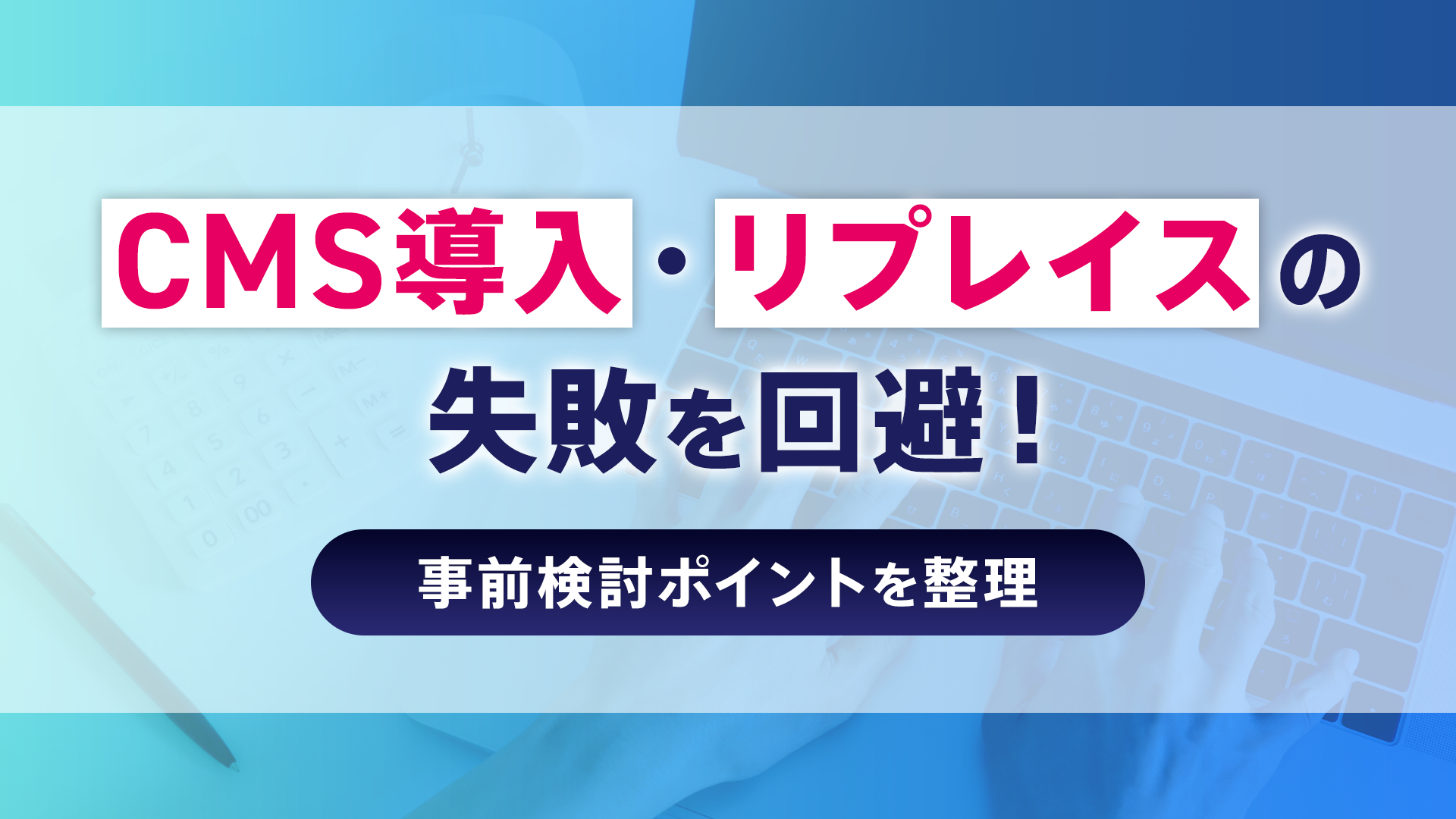
CMS(Contents Management System)の導入・見直し時に発生しやすい課題を整理し、要件定義・運用設計・関係者連携まで網羅した検討項目の内容を解説します。
CMS選びにおける目的、現状分析、機能要件、体制構築などの視点を整理することで、社内合意やベンダーへの相談が円滑に進み、導入後のリスクも低減します。また、実務に活かせるチェックリストも紹介します。
Webサイトのコンテンツを管理・更新するCMS。Web運用の中核を担う重要なツールですが、導入プロジェクトは属人的、場当たり的に対処しがちです。また、CMSは情報システム・広報・現場など部門をまたいで関係者がいるため、初期の検討不足が後の混乱を招く可能性も避けられません。関係部門のなかでもマーケティングや営業施策など影響を及ぼす業務まで洗い出したうえでの選定が必要です。
CMS導入・リプレイスは、Web・IT・マーケティング・広報・経営層など、複数部門が関わる横断的なプロジェクトです。それぞれの部門で、Webサイトに対する目的や期待が異なり、情報発信・ブランディング・営業支援・採用強化など多岐にわたります。
そのため、具体的な課題や改善ポイントや優先順位が整理されていないと要件がまとまらず混乱が生じます。加えて、CMSは多機能であるがゆえに、優先事項や関係者間の役割分担が曖昧になり、要件全体が不明確になりがちです。
要件や評価基準が曖昧で、将来を見据えた判断ができないとベンダーの比較が難しくなります。
もし、自社に合っていないベンダーを選定してしまった場合、要件定義や仕様のすり合わせが上手くいかず、導入やリプレイスに想定以上の時間がかかるかもしれません。ベンダー側も的確な提案ができず、ヒアリングが長期化し、「とりあえずWordPressで…」といったような、汎用的なCMS提案になる可能性もあります。
ベンダーが提案したCMSが自社の運用体制や目的に合っていないまま導入されると運用後は拡張性がなく、サポートや保守で追加コストが発生し、最悪のケースは導入・リプレイスのやり直しにもつながりかねません。
CMSに対する期待や知識の深さ、関心のある内容が部門ごとに異なり、それが温度差につながります。各部門の目的・課題・リスクがバラバラなため、要望が整理されないまま「CMSを変えたい」という話だけが先行し、プロジェクト全体の合意形成に大きな影響が出ます。
CMSの導入・リプレイスの検討時は、目的・現状把握が重要です。デジタル庁の「第3回 政策評価・行政事業レビュー有識者会議資料 ① 政府共通ウェブサイトについて」では「利用者視点で利便性向上、システム担当者視点で費用/負荷軽減を目指す」とされています※1。
企業のCMS導入でも同様の視点を持ち、その要素を(目的と目標、サイトの現状、ターゲットなど)分けてチェックします。
※1:出典「第3回 政策評価・行政事業レビュー有識者会議資料 ① 政府共通ウェブサイトについて」(デジタル庁・2023)
デジタル庁の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」では、要件定義について、「機能要件、非機能要件及び情報システムの実現案についても、情報システム部門のみで決定するものではなく、制度所管部門、業務実施部門を含めたPJMO全体で決定することが不可欠であることに留意すること」とされています※2。
さらに、データ移行に関しては、内閣サイバーセキュリティセンター「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」にて、「情報システムの開発環境、テスト環境から本番運用の環境への移行時において、情報システムに保存されている情報の取扱手順の整備、人為的な操作ミスを防止するための手順・環境の整備、移行の際に関連システム停止が伴う場合には可用性確保のための環境整備等が必要となる」とされており、一層の慎重さが求められています※3。
公的なガイドラインが示すように、CMS導入・リプレイスの成功には2つの要点があります。
第一に、要件定義は情報システム部門だけでなく、実際にCMSを利用する業務部門を巻き込んでおこなうべきということです。これにより技術的な正しさだけでなく、現場のニーズに即した実用的なシステム選定が可能になります。
第二に、データ移行は、事業継続を左右する高リスクな作業として、慎重な計画が不可欠ということです。人為的ミスやシステム停止のリスクを管理し、徹底した事前準備をおこなうことで、ビジネスへの損害を最小限に抑えることができます。
※2:出典「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル庁・2023)
※3:出典「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」(国家サイバー統括室・2021)
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/guide2021_draft.pdf
データに関しても現状の既存サイトをしっかり棚卸して確認し、移行に備えます。ページ数が膨大である、または構造が複雑である場合、作業量や移行ツールの費用が大きくなることがあります。現状のページ数や構成、サイトマップの有無を把握しておくことで、事前に見積もりやスケジュールに反映でき、無理のない導入計画が立てられます。
さらに、移行対象のデータ形式や連携先の仕様によっては、一部のCMSでは対応が難しいケースがあるかもしれません。このような状況を防ぐためにも、データの状況を明らかにしておくことで適切なCMS選定が可能になります。また、既存サイトを棚卸しする過程では、不要なコンテンツの削除や情報設計の見直しも可能です。
これにより、移行後のサイトは、より洗練された構成へと再構築され、コンテンツの品質向上にもつながります。
導入計画
スムーズなプロジェクト進行のために導入計画に関わる内容を明確にします。全体の進行速度や方法に大きく関わる導入期限や、その変更の可否、社内の体制は事前確認してから進行しましょう。
CMS導入は単なるツールの切り替えではなく、社内外の調整を伴います。社内の意思決定フローやレビュー体制、関係部門の関与レベルを把握しておくことで、関係者への説明や調整の手間を最小化して円滑な推進ができます。そして、費用・予算の上限や社内で担えるリソースの有無は、自社と外部委託先との役割分担を判断する材料です。
また、導入時のコストだけでなく、ランニングコストに対する許容範囲や希望を確認することは、CMS選定や契約方式にも関わってきます。
CMSの安定運用には、技術的な側面だけでなく、しっかりとした運用体制の構築が不可欠です。この点について、組織の規模や業種を問わず、情報システムを運用する上での普遍的な原則が、公的なガイドラインに示されています。
例えば、内閣サイバーセキュリティセンターが策定した「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン」には、「情報システムの運用を継続する責任者は、情報システム運用継続計画の策定・運用に幹部層を含めた必要な要員を定めること。各部署のシステム担当者が検討に加わる場合には、判断基準や指示命令系統の調整等や委託先等の関係者との連携方法を調整すること」と記載されています※4。
このガイドラインは、政府機関を対象としています。しかし、そこで語られている「システムの安定稼働には、明確な役割分担と指示系統が不可欠である」という本質は、組織の形態を問わず、あらゆる情報システム運用に共通する普遍的な原則です。
民間企業のCMS運用においても、コンテンツを制作する事業部門、インフラを管理するIT部門、そして外部の制作会社など、多数の関係者が存在します。責任の所在が曖昧だったり、緊急時の連絡系統が整備されていなかったりすれば、些細なトラブルがビジネスに深刻な影響を及ぼす重大なインシデントに発展しかねません。
つまり、このガイドラインは、公共サービスの継続性という極めて高いレベルで磨かれた「リスク管理の最適解」であり、民間企業が自社のWebガバナンス体制を構築する上で、非常に有益な手本となるのです。
例えば、コンテンツの最終承認者や、緊急時のエスカレーションルート、外部制作会社との連携ルールといった役割分担と意思決定のプロセスを事前に定義しておくことが、導入後のスムーズな運用を実現する鍵となります。
※4:出典「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン」(国家サイバー統括室・2021)
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/itbcp1-1_3.pdf
プロジェクト関係者の構成や体制の確認も円滑なプロジェクト推進には必要です。早めの選定が必要なのは、プロジェクトの実務を進める、中核となる推進メンバーです。ここが決まらないとプロジェクトが遅延し、品質の低下を招くおそれがあるため、リソースは十分であるか事前に慎重に確認し、足りなければ調整します。
そして、方針のぶれや意思決定の遅延につながるため、導入における社内承認者や導入を主導する部門も明確にします。また、権限設計やワークフローの設計に関わるコンテンツ管理部門の関係者の確認も必須です。

上記のCMS検討時にチェックするべき項目を確認することで、得られるメリットを整理します。
複数部門が関わっていても、共通した確認項目をもとに話し合いを進めることが大切です。これにより、社内のCMS導入・リプレイスに対する意識や課題を共通言語で整理できます。こうした基盤があれば、新たな課題や方針変更が発生した場合でも検討項目を軸に議論しやすく、重視すべきポイントや優先順位の認識を擦り合わせる上で有効です。
また、各部門間で意見のズレや誤解を減らし、合意形成のスピードを高める効果も期待できます。その結果、プロジェクト初期段階に起こりがちな混乱や検討のブレが抑制され、より実効性の高い意思決定につながります。
初めて依頼するベンダーや制作会社の場合でも、自社の状況や目的が整理されていればやり取りもスムーズです。たとえば、導入背景や目的、現状の課題、求める機能や体制といった情報が明確になっていれば、ベンダー側も課題の本質を早く把握でき、提案の的確さやスピードが向上します。
また、こうした整理された情報は、複数社を比較検討する際にも有効です。共通の基準で比較ができ、判断材料がブレにくくなるため、選定プロセス全体の効率と精度が高まります。
CMS導入をスピード優先で進めてしまうと、ユーザビリティの低さや業務フローとの不適合、他システムとの連携性の欠如といった導入後のギャップやトラブルが発生しやすくなります。事前に導入対象サイトの現状や目的、必要な機能、関係者の役割分担など、検討すべきポイントを網羅的に整理しておくことで、こうした想定外な事態を最小限に抑えることができます。
また、初期の段階で必要な確認をしておけば、導入後の運用フェーズにおけるムダな手戻りや追加コストの発生を防ぎ、スムーズかつ継続的に運用できる基盤の構築にもつながります。
CMS導入・見直しが発生したら、制作会社・CMSベンダーへ相談する前に、上記内容を参考に目的や現状分析、必要とする機能を事前に確認しましょう。必要な情報がまとまったあとに相談するとスムーズに進行します。また、導入・リプレイスでお悩みの際は、伴走パートナーとなる制作会社・CMSベンダーを探すか、当社によるCMS選定・設計・導入・運用まで一貫したご支援も可能です。
今回説明した内容が網羅されたチェックリストは、こちらよりダウンロード可能です。社内での要件のすり合わせやベンダーとの相談時にお使いいただける内容となっています。まずは、チェックリストの内容を基に自社の状況の棚卸をおこなってみてください。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。