執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
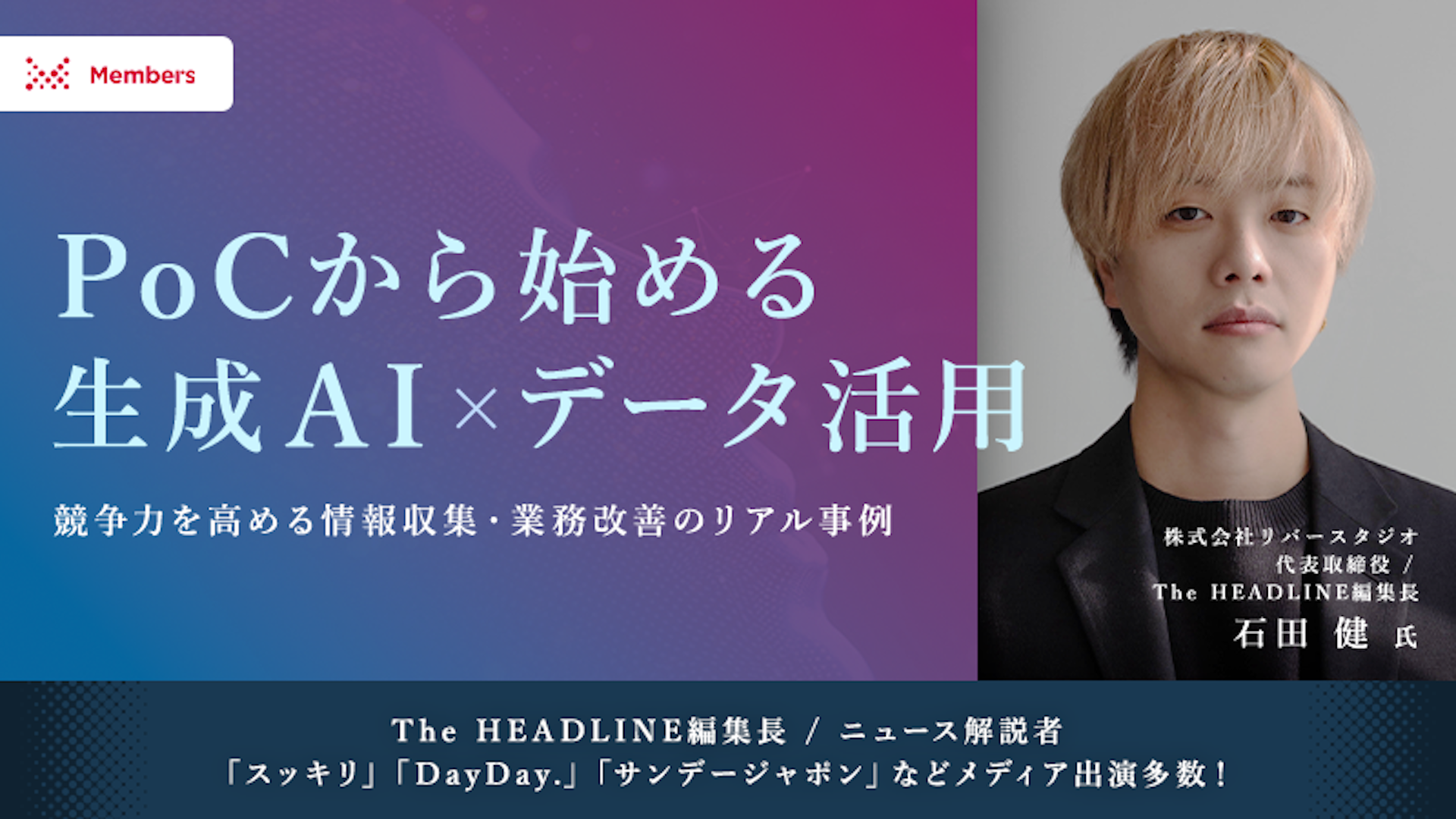
近年、AIを活用した分析や業務効率化へのAI活用に関心が高いものの、「どこから始めればいいかわからない」「効果が見えにくい」と感じている方が多くなっています。
そのような悩みを抱えている方に向け、2025年4月に株式会社リバースタジオの代表取締役 石田健氏をお招きしてAIを活用したデータ収集や業務改善についてお話しいただくオンラインセミナーをおこないました。その内容を一部抜粋してご紹介します。
登壇者 株式会社リバースタジオ
株式会社リバースタジオ
代表取締役/The HEADLINE編集長
石田 健氏
ニュース解説メディア The HEADLINE 編集長。日テレ系「DayDay.」などTVや雑誌、ラジオなど多数番組でコメンテーターを務める他、J-WAVE「JAM THE PLANET」パーソナリティも担当。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程(政治学)修了後、創業した企業を東証プライム上場企業に売却して現職。テクノロジーや人権イシュー、政治思想、東アジアの近現代史などに関心。
 株式会社メンバーズ
株式会社メンバーズ
AIフォーオールカンパニー社長
瀬崎 正太郎
メンバーズ2014年入社。大手金融機関のプロデューサーとして、システム開発プロジェクトやデジタルカメラマーケティング支援を担当。2023年に生成AI推進チームを立ち上げ、2024年よりマネージャーとして従事。メンバーズにおける生成AI活用支援サービスを推進し、企業が抱える課題を実践的に解決するための研修やコンサルティングサービスを提供。2025年4月には新設された社内カンパニー「AIフォーオールカンパニー」のカンパニー社長に就任。生成AIを活用したビジネスプロセス変革やAIエージェントの導入を中心に企業のAI活用を促進し、企業の競争力強化に貢献していくことを目指しています。
モデレーター 株式会社メンバーズ
株式会社メンバーズ
生成AI推進室リーダー/AIディレクター
澤井 里奈
プロモーション支援や人材育成、DX推進を支援するサービス開発に従事した後、2023年より生成AI推進室にジョイン。現在は、企業における生成AIの利活用推進を加速させるため、研修・ワークショップの企画運営や、生成AI活用のお悩み相談会を通じた実践的な支援を行っています。特に、デジタルマーケティング領域での生成AIやAI活用による顧客体験の向上や、データを活用したパーソナライゼーションに深い関心を持ち、AIの力を活かしてビジネス変革を実現することを目指しています。
前半は、リバースタジオ石田氏のセッション「⽣成AIを活⽤したデータ収集とビジネスインパクト」からスタートしました。
現在、AIやAIエージェントの活用が多くの業界・企業で始まりつつあります。それによって起きている大きな変革は、非構造化データを使って逐次タスクを処理できるようになったという点です。
AIは、SNSの投稿文のように「今日朝起きました」「朝起きてご飯を食べました」「ご飯に味噌汁が付いていました」といった自然言語で書かれた文章であっても処理することができます。この変化は、生成AIがもたらした最初の大きなパラダイムシフトです。さらに、近年はこのパラダイムシフトに加え、タスクの逐次処理ができるAIエージェントが登場しました。
例えば、業務の処理の過程で何かエラーや問題が起きた際に自律的にステップ・バイ・ステップで考え、修正し、さらにその修正を繰り返し実行することが可能になりました。業務のなかにも大きな変化が起き、業務を完全自動運転できるような世界に確実に近づきつつあります。

最初に「データ・パイプラインの自動化」という、人手を介さず自動でデータ関連のタスクを実行する仕組みについて説明します。マーケティングのための大量データの分析、あるいはソーシャルリスニングで大量のデータを見たいというときに実行命令を出すと、データをソースから取ってきて外部APIかSQLの実行をします。
次にそれが正しいかどうかを処理・評価して、そのうえでタスクを完了するのか、あるいはもう1回再実行するのかを決めます。そして、データの処理・加工をして格納して最後に活用します。この流れを自動でAIエージェントが実行してくれる、というのが根本的な世界観です。

情報・データ活⽤の具体的イメージについて、実際の業務を例に挙げて説明します。実は、企業のあらゆる部門においてデータや情報を活用することができます。
以下の表の1行目のような、カスタマーサポートのログのAI分析、2行目の問い合わせ履歴に基づいてよくある質問の自動生成、5行目のニュースやSNSのテキストマイニング、9行目の過去の取引履歴から契約更新の予兆検知、12行目のバグの報告をクラスタリングするなど、さまざまな活用事例があります。

こちらの表には出ていませんが、アンケートの自由記述のデータを一元に集めてクラスタリングして何かに使うというような、企業に存在するあらゆるデータ、情報を集めて処理をし、最後に活用するという一連のステップがAIエージェントによって劇的に進化しているのが現在であり、それを実務に落とし込むことができるようになりました、というのが本日のセミナーのコアな部分です。
例えば、社内で何らかのナレッジを溜めて、それを検索できるようなシステムを作りたいといった場合、処理の流れは以下の図のようになります。
先ほどのデータ・パイプラインの図と構造は同じで、左上の辺りに「ソースから取得」という処理がありますが、次は「社内ドキュメントを見にいく」「FAQを見にいく」「社内で話した議事録を見にいく」という処理にわかれます。
そのなかでデータが適切に取れているかということを評価し、問題なく取れているなら、「処理・加工」をする。ここで「非構造化データを構造化」や「データ型の変換」をして、「格納」「BIツールへ連携」、最後に活用というプロセスとなります。

これは、ソーシャルリスニングやデータ・パイプラインといった高度な領域ではなくとも、日報のなかにメンタル面の不調があるといったような内容が見られた社員を特定し、その人に適切な支援をしていくというような活用方法もあります。こういったものを1,000名規模でできるようになるというところも含め、データを集めてそれを処理・加工して最後に活用していくというプロセスにのせることができます。
このように、高い自律性や学習力があるAIエージェントによって企業に存在するあらゆるデータ・情報を集めて処理をして、最後に活用するというステップが劇的に進化し、それを実務に落とし込むことができるようになりました。
実のところ、AIエージェントがおこなっていることは従来のDXの考え方とあまり変わりません。業務プロセスをどのように捉え、どの部分を自動化できるか、どの部分をAIに任せられるかというのが根本的な問いだと考えています。
そのため、AIエージェントによる情報・データ活用をする際には、全体シナリオのなかで「これはAIでできる」「これは人間がサポートしないとダメだ」ということをしっかりと分類できるような人材をアサインして業務フローを再設計していくことが非常に重要です。AIに対しての知見、適切な技術の選択、業務に対しての理解の深さ、それが揃って初めてAIエージェント自体の業務フローが確立できます。

おそらく3年後にはAIによる完全自動化の世界がやってくると思います。商品の検索、データを抜き出してエクセルに記載、シミュレーションをパワポで作って資料に落とし込む、というプロセスを全部AIに任せて人間は最後に意思決定をするだけという世界観がおそらく5年後にはかなり一般化していくと思います。
向こう1~2年は、請求書管理、稟議、先ほどお伝えした日報の自動化、そういった領域で取り入れられていくと思いますが、それが向こう5年になったときに『社外データと組み合わせよう』『大規模データと組み合わせよう』『社外とのやり取りのプロセスと結合してしまおう』そんな世界観が確実にやってきます。
そこで必要なのは、メンバーズの得意領域である、技術と専門的な知見を備えた人材によって解決することです。業務フローを理解し、そのために適切な人材をアサインし、全体シナリオを作り、適切な技術スタックを選定する。今は、GPT・Cursor・RAG・Claude・Gemini etc…というAIに関するワードや注目されているバズワードが飛び交っていますが、結局のところ技術スタック選定の前に、それをどうやって業務に浸透させていくのか、業務フローは何なのか?業界理解・経験はあるのか?DXの経験は?そういった経験が問われてくる。
そういう意味では、人材に求められているケイパビリティは従来と変らないとは思うのですが、AIエージェントが出たことで格段に進化が早くなっていくので、技術にも明るい、業界にも明るい、そういった人材の重要性が進んでいるというのが実際に支援させていただいている企業さまのなかでも共通見解として出てきている印象です。
セミナー後半は、当社内に2025年4月1日付で設立された、企業のAI利活用におけるコンサルティング、エンジニア人材を提供するAIフォーオールカンパニー社長の瀬崎から「AIエージェントの活用とPoCから始める実践アプローチ」について解説しました。
「2025年はAIエージェント元年」と評されるなか、Gartnerの調査※1によれば、2028年までに日本企業の約60%がAIエージェントを導入し、従来の機械的タスクを自動化する見通しです。達成度は不確定ではあるものの、現在は補助的ツールにとどまるAIが、今後はビジネスのコアプロセスへ深く組み込まれていくことは確実視されています。
AIエージェントとは、周辺環境を認識し、その情報に基づいて自律的に意思決定をおこない、適切なアクションを実行するシステムを指します。主な特性は以下の4点です。
AIエージェントは設計段階から外部システムとの接続を前提としており、API経由で情報取得や処理を実施できる点が、大きな強みとなっています。
生成AIとデータ活用により情報収集・業務改善の手法が急速に変革する一方、「AIエージェントを導入しても業務に定着し成果が出るのか」「どこから着手すべきか分からない」といった不安の声も少なくありません。こうした課題に対し、当社はPoC(Proof of Concept:概念実証)を起点とするスモールスタートを推奨しています。PoCは短期間でプロトタイプを開発・検証し、その有効性を見極めるアプローチであり、次の2つのメリットがあります。
PoCは「完璧なシステム」を構築する場ではなく、期待効果を迅速に検証する実験場です。小さな成功を積み重ねることで、AI導入に対する社内理解と協力体制を強化し、段階的な展開へとつなげていきましょう。

AIエージェントの普及により、業務プロセスの効率化・自動化、意思決定の高度化、さらにはカスタマーサポートの品質と応答速度の向上が期待されています。こうした自動化・高度化の進展は人的リソースの活用領域を拡大し、より創造性の高い業務や高付加価値タスクへ注力できる環境を実現すると予測されます。加えて、AIエージェント自体を核とした新たなビジネスモデルの創出により、新規事業機会が生まれる可能性も指摘されています。
一方で、自律性の高いエージェントを運用するほど情報セキュリティとデータプライバシー保護のガードレール強化が不可欠です。リスクマネジメントを含む統合的な対策を並行して講じることが、持続的な導入と活用の鍵となります。
本セミナーでは、生成AIおよびAIエージェントの業務適用に関する最新動向と、PoCによるスモールスタートの重要性を概説しました。情報収集や業務改善のアプローチが大きく変革する現在、まずは自社で活用可能な領域を具体的に特定し、短期間で効果検証できるテーマを設定することが重要です。
とりわけ、業務フローが明確でデータ基盤が整備された領域から着手すれば、小規模な成功体験を積み重ねることで社内理解と協力体制を強化できます。AI活用は一過性のブームではなく、将来の競争優位を左右する戦略的投資です。本レポートの知見を関係部門と共有し、自社におけるPoCテーマの選定から始めてください。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。