執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
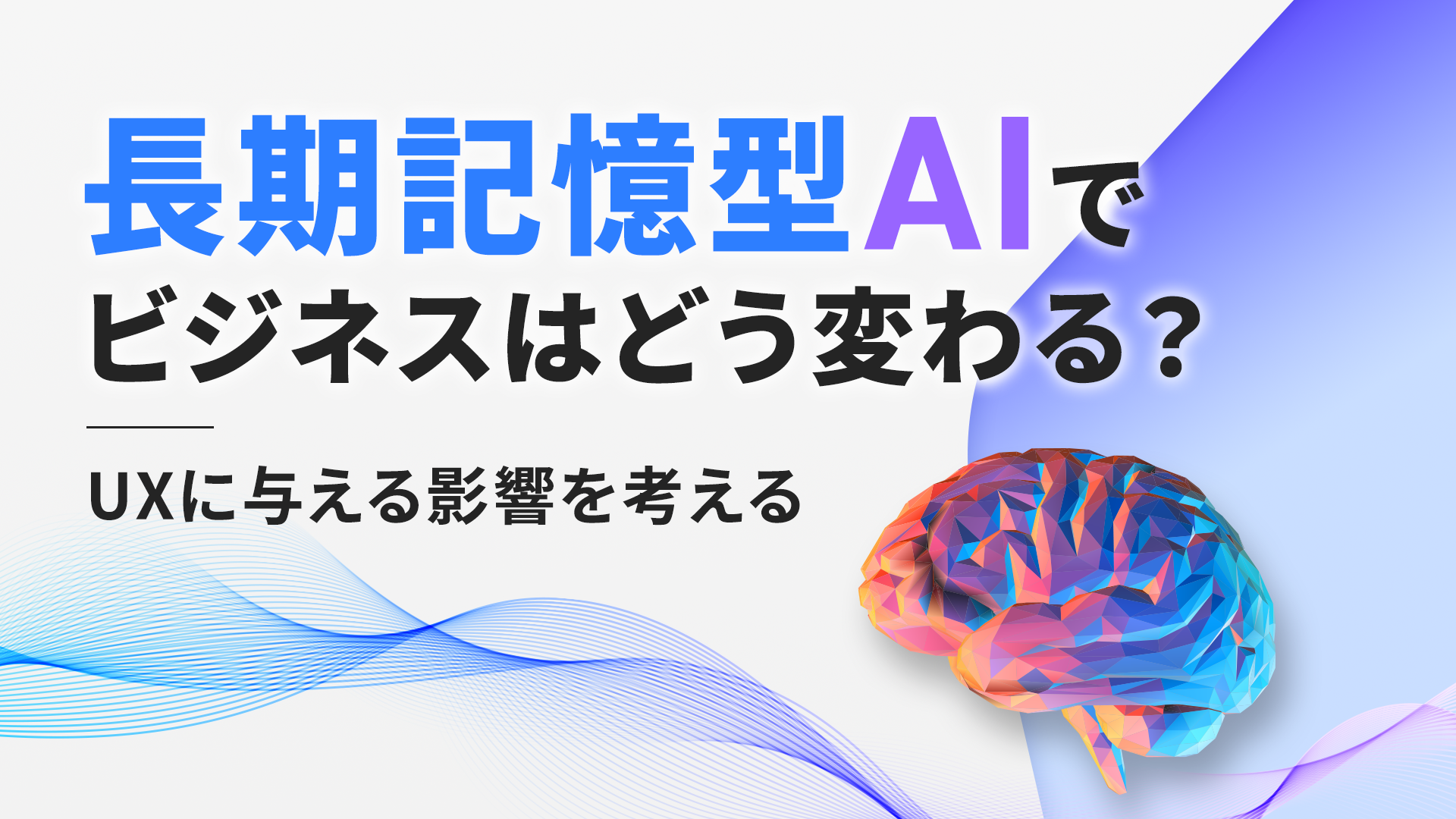

銀行、保険、不動産、行政など、複数のチャネルや手続き、アプリケーションにまたがる業界では、「毎回ログイン」「都度の情報入力」「初回説明の繰り返し」といったUXの断絶が常態化しています。ユーザーにとってはゼロベースの体験が続き、企業にとっても接点の継続性や満足度向上に限界を感じる場面が増えています。
この課題の背景には、「記憶される接点」が存在しないというUX構造上の問題があります。現在の多くのシステムは、チャネルやサービス単位で体験が組まれており、前回のやり取りや蓄積された情報が別の接点に引き継がれないまま、ユーザーに繰り返しの負担を強いているのが現状です。
PwCは、この状況について「体験がカスタマージャーニーベースで一貫していないこと、統合されたエクスペリエンスが提供できていないこと」が、日本企業の顧客体験における課題の一つである、と指摘しています。
こうしたUXの構造的な課題に対して、行政領域ではAIを活用した対話型のUXが実装され始めています。 情報通信白書(令和7年)には、行政サービスにおけるAI活用の方向性として、高齢者や外国人に向けた「対話的な案内」や「多言語での情報提供・相談支援」の重要性が明記されています。
また、デジタル庁が推進する自治体窓口DX「書かないワンストップ窓口」では、マイナンバーカードや自治体が保有する情報を基に、申請書の事前入力を自動化し、署名のみで手続きが完了するUXがすでに一部導入されています。
音声認識や自然言語処理、チャットボットなどのAI要素は、現時点では先進自治体に限定されますが、ユーザーの操作負荷を最小限に抑え、情報の再入力を不要とする「記入レス・ノンストップ体験」は、記憶を活かすUXへの過渡期的な実装として注目されています。
対話型AIの進化は、ユーザー体験(UX)の前提を変えつつあります。Accentureは、対話型AIが単なる情報検索ツールから、質問に答えるUI=顧客接点へ進化していると指摘しました。人々は、意識しないうちに従来の検索行為から、自然な質問や相談へと行動をシフトさせつつあります。それに伴い、企業は生成AIチャットボットなどを活用して、新たな顧客接点の構築を進めています。
これは、UXの起点が入力や操作ではなく、会話や文脈理解に移行しつつあることを意味しています。ユーザーの行動に応じてAIが最適な回答や行動提案を返す。そんな双方向の関係性が、UXを定義しているのです。
McKinseyは、「AIエージェントが複数ステップにまたがるワークフローを処理し、リアルタイムで文脈を理解しながら実行できる」とレポートで指摘しています。こうしたエージェントは、業務の一部を担うバーチャル同僚として機能し、レビュー業務の工数を20〜60%削減した事例も報告されています。
この進化の背景には、AIがユーザーごとの対話履歴や行動パターンを記憶し、それに基づいて的確な支援を提供できるようになったことがあります。短期記憶に加え、セッションを超えた長期記憶の活用が、AIエージェントの実用性を大きく高めているのです。
Gartnerは、2025年の戦略的テクノロジートレンドの一つとして、「アンビエント・インビジブル・インテリジェンス(Ambient Invisible Intelligence)」を挙げています。これは、テクノロジーがユーザーの操作や意識を介さずに環境に溶け込み、状況や文脈に応じて最適な体験を自動的に提供するUX構造を指します。
このコンセプトでは、IoTやAI、機械学習、文脈認識型コンピューティング(context-aware computing)などの技術を組み合わせることで、ユーザーが明示的に操作しなくても、必要な情報や機能がタイミングよく提供されることを目指しています。UXは「画面を開いて操作するもの」から、「生活や業務に自然に溶け込む体験」へと進化しつつあります。こうした変化は、今後のUXを考える上で避けて通れない潮流となりつつあります。
このように、生成AIとそれを支える長期記憶技術、AIエージェント、文脈認識コンピューティングの進化により、UXは操作から関係性へ、さらに「予測された行動支援」へと進化しています。企業は、これらの前提を踏まえつつ、ユーザー体験を考えていかなければなりません。
生成AIの進化、とくにマルチモーダル技術の高度化も、UXに大きな影響を与えます。PwCは、複数のモダリティ(音声・画像・テキスト・感情など)を統合的に処理するAIの登場により、ユーザーの文脈や感情を捉えたうえで、重要な情報を選別・保持する半永続的記憶の実装が可能になると指摘しています。
AIは、ユーザーごとの対話や行動の蓄積をもとに、個別の文脈を理解しながら継続的な支援をおこなう存在へと進化しつつあります。UXはもはや単なるインタフェースにとどまらず、AIとの記憶と関係性をいかに築くかという本質的な問いへと移行しているのです。
こうした「記憶を前提とした体験」が現実味を帯びる一方で、現在のUXの多くは依然として短期記憶ベースのAIを前提に考えられています。現在主流の大規模言語モデル(LLM)は、1回のプロンプトや会話内でのみ情報を保持する「短期記憶」ベースのモデルで、過去の対話文脈やユーザーの嗜好を継続的に活用することは困難とされてきました。
こうした制約に対し、PwCは、2035年までに推論時スケーリングや自己学習能力の向上によって、こうした制約を超えるUXのあり方そのものが大きく変わると予測しています。対話の継続性やユーザー特性の蓄積が前提になるにつれて、AIは「ユーザーが使い方を学ぶツール」から、「ユーザーを理解し、記憶する存在」へと進化していくのです。
AIが長期記憶を保持するUXが実現すると、どの情報を保存するか、いつ更新するか、いつ忘れるべきかといった運用もガバナンスの対象となります。これらは従来のUI/UXでは扱われてこなかった論点であり、技術部門・CS部門・法務・データガバナンスなどを横断した体制を組んでいかなければなりません。
PwCはこの変化を「シンビオティック・エンタープライズ(共生型企業)」と表現。AIが顧客交渉履歴や業務パターンを記憶・継承し、ヒトは創造性や倫理判断を担うという新たな分担の構図を提示しています。

記憶を活用するUXの構造変化は、あらゆる業界において、異なる形で現れ始めています。ここでは、具体的にどのようなインパクトや適用可能性があるのか、業界別に見ていきます。
金融サービスでは、口座開設、資産運用、ローン申込、保険の見直しなど、複数の手続きがライフステージをまたいで発生します。これらのプロセスにおいて、顧客の属性や意向を毎回一から取得・確認するUXは、企業にとって大きな効率課題であり、利用者にとっても煩雑な体験となっています。
長期記憶型AIを活用することで、過去の相談内容、資産状況の変化、ライフイベントに関する情報を文脈ごとに保持し、それらに応じたサービスの再提案や、タイミングに応じた支援が可能になります。顧客との接点で継続的な理解が働くUXを実現することで、金融機関は「理解してくれている存在」として関係性を築くことができ、顧客体験(CX)全体を根本から高めることがえきるようになります。
不動産業では、賃貸から購入、住み替え、売却といったプロセスが長期にわたって発生します。これらを通じて、顧客は希望条件や生活環境、家族構成といった要素を何度も共有する必要があり、その都度おこなうヒアリングや再入力がUX上の大きなハードルになっています。
長期記憶型AIがこれらの履歴や嗜好を蓄積し、変化に応じたタイミングで適切な情報を提案できれば、利用者の負担を軽減しつつ、一貫したUXができます。
製造業の現場では、機器の保守・点検対応において属人的な判断や記録のばらつきが課題となっています。これまでの対応履歴や設備ログが共有されず、トラブルのたびにゼロベースでの確認が必要となる状況では、効率も品質も安定しにくいという問題があります。
長期記憶型AIがこうした過去の情報を継続的に記憶・参照し、「いつ、どのような事象があり、どう対処したか」といったナレッジを提示することで、業務の標準化と技術継承が可能になります。これは、ベテランの判断力をAIに継承し、予測的なメンテナンス対応を支援するUXの土台になります。
AIが過去の文脈を保持し、一人ひとりのユーザーや、個々の設備・取引を理解する存在として機能する──そのような新たなUXは、業界を問わず、顧客接点や現場対応の構造そのものを変えていきます。UXの未来像は、記憶と文脈に根ざした継続的な関係性のなかにあると言えるでしょう。
前章で紹介した金融・不動産・製造といった各業界の動向からも明らかなように、分野を問わず、ユーザーや現場との継続的な関係性を前提としたUXが重視されるようになります。長期記憶や文脈保持、対話の継続性を備えたAIは、従来の「入力・検索・操作」を中心としたUXから、「自分のことを理解してくれている」と感じられる存在へと進化しつつあります。
こうした変化は、PwCが提唱する「シンビオティック・エンタープライズ(共生型企業)」の考え方にも通じます。AIが業務履歴や顧客対応の履歴を記憶し、それに基づいて自律的に業務を担う一方で、人は創造性や倫理判断といった本質的価値に集中する──そんな新たな分業モデルへの移行が求められているのです。
こうした変化に適応するには、企業の側も従来の前提を見直し、新たな視点からの取り組みが不可欠です。ここでは、特に重要となる3つの観点を整理します。
いま、企業にはUXを「記憶される体験」へと再定義し、AIとともに価値を育む基盤を、部門横断で構想・構築することが求められています。それは、単なる技術の導入にとどまらず、顧客との関係性をいかに再構築するかという、本質的な問いへの挑戦でもあります。記憶するAIが描く未来に備え、いまこそUXを企業戦略の中核として捉え直すときです。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。