執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
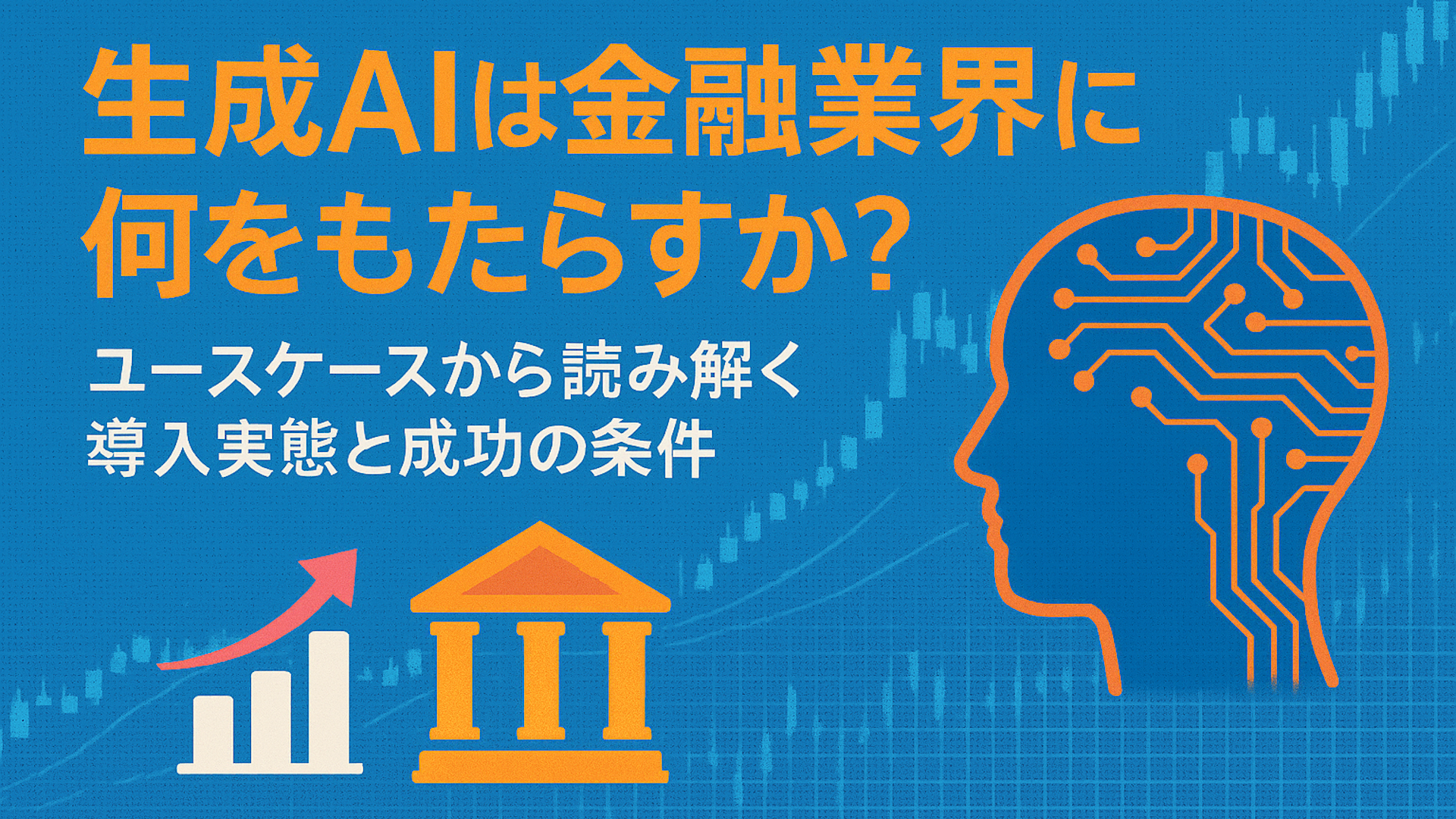
近年、生成AIの技術は急速に進歩し、金融業務の効率化や新たなサービス創出への期待が高まっています。一方で、ハルシネーション(AIの判断の誤りや情報の偏り)や、サイバー攻撃などのリスクも指摘されています。
そこで金融庁は、金融機関がAI活用のメリットを最大限に引き出しつつ、リスクに適切に対応できるよう、論点を整理し、広く意見を求めることを目的に「AIディスカッションペーパー(第1.0版)」を公表しました。金融庁は、AIを活用しないことによる競争力低下といった「チャレンジしないリスク」も重要視しており、イノベーションを阻害しない形でのルール作りを目指しています。
本コラムでは、このAIディスカッションペーパーに記載されたAI活用の現状とユースケースに着目。特に、生成AI領域のユースケースごとに成功事例を紹介します。

AIディスカッションペーパー※1は、2024年10月から11月にかけて、金融機関130社に対して金融庁が実施した「金融機関等のAIの活用実態等に関するアンケート調査」に基づいています。このなかでAIを何らか利用している金融機関のうち、7割以上が幅広く一般社員向けに生成AIの活用を認めているとのこと。
RAG(Retrieval Augmented Generation)の活用、ファインチューニングによる利用、汎用の生成AIをそのまま利用など、導入形態はさまざまながら、生成AIを積極的に利用する傾向にあるようです。そして、AIディスカッションペーパーでは、利活用の目的に応じてユースケースを以下の3つの類型に整理されています。
社内利用(業務効率化など)
対顧客サービスへの間接的な利活用
対顧客サービスへの直接的な利活用
この類型ごとに、ユースケースと成功事例を見ていきます。
※1:出典「AI ディスカッションペーパー(第1.0版)」(金融庁・2025)
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250304/aidp.pdf
「文書の要約」、「翻訳」、「文書などの校正・添削・評価」の3つのユースケースは既に7割以上の金融機関などが導入済であることが明らかとなっています。金融機関は大量の文書を作成・保有しており、文書関連のユースケースは社内利用においてもっとも一般的といえるでしょう。
三井住友海上火災保険株式会社と日本電気株式会社(NEC)は、事故対応業務において、顧客との通話内容を自動でテキスト化し、生成AIで要約するシステムを開発。NECの音声認識技術と、Microsoftの「Azure OpenAI Service」を組み合わせて構築されています。
従来、担当者が通話内容を手作業で記録し登録していましたが、この作業には多くの時間がかかり、顧客に迅速かつ丁寧な対応をするため、業務の効率化が求められていました。このシステムにより、担当者は内容の確認のみとなり手作業の負担が軽減され、創出された時間を顧客対応に充てることが可能となります※2。
※2:出典「事故対応に生成AIの文章要約技術を導入」(三井住友海上火災保険株式会社/日本電気株式会社・2024)
横浜銀行は、日本アイ・ビー・エムと協力して、融資審査業務における稟議書の作成に生成AIを活用する実証実験を実施しました。融資審査業務では行員のヒアリング力や提案力の底上げが必要不可欠であり、そうした活動時間を創出するための業務効率化が強く求められています。
今回の実証実験では、「融資稟議書作成支援AI」のプロトタイプを作成し、生成AIが稟議書作成を支援することで、行員の稟議業務にかかる時間の効率化が確認でき、今後業務に実装した場合、最大で年間19,500時間の業務効率化が見込まれるとのことです。加えて、与信判断に必要な審査項目について、顧客へのヒアリングが不足している点を明確にできる効果も確認できました※3。
※3:出典「『生成AIを活用した融資審査業務における稟議書作成』の実証実験の実施について」(横浜銀行・2024)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7186/ir_material33/240011/00.pdf
みずほ証券は、生成AIを活用した社内文書検索システム「MOAIサーチ」を開発。社内ルールの検索や問い合わせにかかる業務時間を最大約6割(1人当たり約340分/月)削減しています。
開発の背景は、社内ルールや手続き、事務マニュアルなど、約4,000件を超える文書の検索のしづらさ。内容によっては複数の文書をポータルサイトから探したり、見つからなければ所管部に問い合わせたりと業務が煩雑となっており、全社的課題となっていました。
そのため、複数部署を横断する体制のもと、開発が開始されました。リテール業務プロセス改革におけるマニュアル整備や事務マニュアルなどの管理を担う事務企画部、基本方針や規程などの管理を担う経営企画部、システム開発を担うITサービス・プラットフォーム部に加え、社内のDX推進を担うデジタル戦略部がワンチームとなってプロジェクトを推進し、成功に導きました。
機能としては、ユーザーが入力した質問に基づき、AIが関連文書を横断検索し自然言語で回答を生成します。
回答精度を高めるため、RAG手法を採用し、最新の情報から検索した結果を基にAIが回答。また、関連性の高い文書を選定し、検索手法を組み合わせることでAIによるハルシネーションを防いでいます。
ユーザーテストの結果では、解決率は約96%と高い評価が得られました。さらに約98%のユーザーが「継続して使いたい」と回答しています※4。
※4:出典「90%を超える解決率を実現。社内文書検索システム「MOAIサーチ」誕生の道のり。」(みずほ証券・2025)
https://www.mizuho-fg.co.jp/dx/articles/moai-search/index.html
LLM(Large Language Model)は、テキストの解析・生成に特化したAIであるため、社内文書の作成・検索などに最適であり、導入によってかなりの業務効率化が図れることが実証されています。ただその業務品質は、いかに精度を高めるか、ハルシネーションを排除できるかにかかっており、プロンプトの質的向上、ベースとなる文書データの整備がポイントです。
AIディスカッションペーパーでは、この類型の代表的なユースケースはコールセンター業務であるとしています。前述のアンケート調査によると、コールセンター部門に人員を増加することは難しくても、生成AIを導入することで人手に頼らず、かつ顧客への的確な応答ができると回答している金融機関は多いです。
ただし、ハルシネーションなどのリスクを完全に解決することは困難なため、顧客に直接提供されるサービスに活用することは難しいと判断する金融機関が大半のようで、コールセンタースタッフが顧客対応をする際の補助として生成AIを活用する例が数多く見受けられます。
三井住友カードは、同社のコンタクトセンターにおける生成AIの本番利用を2024年7月に開始。この生成AIは、ELYZAが提供するRAG技術を活用しており、社内データを検索して回答の草案を自動的に生成する仕組みです。
導入の背景には、2023年度における新規申し込みが500万件を超え、これにつれて月間約50万件にのぼる顧客問合せに対応するため、対応品質と効率化が求められていました。生成AIを導入することで、オペレーターの対応スピードの向上と、お問い合わせチャネルの強化が実現され、最大で60%程度の対応時間短縮が見込まれています。
※5:出典「三井住友カードとELYZA、お客さまサポートにおける 生成AIの本番利用を開始」(三井住友カード株式会社・2024)
みずほ銀行は、2024年8月に生成AIを活用した次世代コンタクトセンターシステムを導入しました※6。このシステムは、顧客へのサポートやコンサルティングの強化を目指し、利便性と安心感を提供するとともに、コンタクトセンター運営の高度化を実現します。
本システムの開発・導入にあたっては、日本アイ・ビー・エムと、日本語コミュニケーションAIの複数分野でシェアNo.1を誇るPKSHA Technologyと協働。SalesforceをベースとしたCRM機能や各種インターフェースと、最新のAI技術を融合することで、優れた操作性・柔軟性・拡張性を併せ持つ高機能なシステムが完成しました。
AIアルゴリズムの高度化により、FAQやチャットボットの回答精度が継続的に向上し、電話・チャット・LINEなど、あらゆるチャネルの相談内容がコンタクトセンター内で一元管理され、応対内容は自動テキスト化・要約され、営業部店ともセキュアな環境で共有されます。
本システムは、満足度の高い顧客体験を提供することはもちろん、AIを活用してコンタクトセンターのスタッフが働きやすい環境・機能を整備し、スタッフが能力を最大限に発揮できる状態を目指しています。例えば、オペレーターの画面では、顧客の本人確認が済むと即座に顧客情報や過去のコンタクト履歴が表示され、会話はその場でテキスト化。
また、会話に応じたマニュアルやQAが自動的に画面表示され、会話の最中に顧客を待たせることはありません。会話も自動で要約されることで、オペレーターの後処理も迅速になります。
※6:出典「生成AIを活用した次世代コンタクトセンターシステムをリリース。」(みずほ銀行・2024)
https://www.mizuho-fg.co.jp/dx/articles/ai-contactcenter/index.html
このように、コンタクトセンターなどで顧客対応を担当するスタッフをさまざまな形で支援する機能を生成AIで実現することが、対顧客サービスへの間接的な利活用となります。つまり、顧客の取引履歴やコンタクト履歴、会話に関連するサービス内容の表示など、スタッフへの情報支援をタイムリーにすることで、結果的に顧客への対応品質の向上につながります。
こうした情報支援によって、スタッフは経験を問わず質の高い顧客対応ができるようになり、オペレーター不足の解消にもつながるという点が大きなメリットです。
この類型についてAIディスカッションペーパーには、「ハルシネーションのリスクや、生成AIに関する各金融機関等でのガバナンス体制に関する整理が途上であることを踏まえ、顧客に直接サービスが提供される分野においての生成AI利用についてはより保守的に運用している金融機関等が大半である。ただし、一部のフィンテック事業者などにおいては、ライフプランのアドバイスなど、既に生成AIのアウトプットを顧客に直接提示するサービスの提供を開始している。」と記載されています。
一般社団法人Fintech協会に加盟し、AI・ビッグデータサービス事業を展開するMILIZEは、ライフプランシミュレーションmilize Liteに、生成AIアドバイス機能を追加しました。その背景は、昨今の金融市場は、低金利、インフレ、グローバル市場の不確実性や地政学的リスクが混在するなど、急速な変化を遂げています。さらに顧客の価値観やニーズの多様化により、資産運用やライフプランニングに対して、これまで以上に柔軟かつ個別化されたアドバイスが必要とされているためと説明しています。
生成AIアドバイス機能の追加により、ユーザーは貯蓄額やライフプランなどの簡単な質問への回答を入力するだけで、貯蓄と投資のバランスや節約などに関するパーソナライズされたプランを瞬時に得ることができます。
※7:出典「MILIZEが、ライフプランシミュレーション「milize Lite」に生成AIアドバイス機能を追加」(MILIZE・2024)
投資AIアシスタントは、楽天証券が同社のWebサイト・コンテンツとChatGPT4.1※8組み合わせたオリジナルのAIチャットボットです。これから投資をはじめようという初心者が、例えば「新NISAについて知りたい」「口座の開設方法は?」などチャットに質問するだけで同社のWebサイトから回答を返してくれます。
現在、一般公開されてはいるものの、「ベータ版+プラス」として、試験運用中となっています※8。
※8:2025年8月時点の情報です。
※9:出典「はじめての投資を応援!投資AIアシスタント」(楽天証券・2024)
https://www.rakuten-sec.co.jp/assistant/
この2つの事例の違いを比較すると、MILIZEの場合は、あくまでライフプランのシミュレーションやアドバイスのため、貯蓄や投資などのアクションは最終的には利用者の判断になります。
一方、楽天証券の事例では、同社のWebサイトコンテンツに情報ソースを限定しているものの、投資のための情報提供であるのが特徴です。そのため、ハルシネーションが原因で金融商品をユーザーが購入した場合、リスクとなり得ます。注意事項には、「不正確な情報や、お客さまによってはご不快と感じる情報が出る可能性があります。」との記載があり、公開から数ヵ月たっても試験運用中としているのは、こうしたハルシネーションのリスクを考慮しての判断と言えます。

業務内容・プロセスをタスクレベルに詳細化し、生成AIの得意領域を見極めることが重要です。導入目的に合わせて、もっとも有効なタスクをAIに割り当てます。
三井住友海上火災の事故対応の事例では、「通話内容の自動テキスト化と要約」が該当します。これまで担当者がメモをとったり、通話後に対応内容を文書にまとめたりといった作業がなくなることで、顧客との通話に専念でき、顧客満足度の高いコミュニケーションが実現しました。
個人の作業効率化や部署ごとの業務でのPoCが進められ、ある程度の成果が出ているとAIディスカッションペーパーにも記載があります。こうした成果を踏まえ、これから全社レベルのプロジェクトが始動することが予想されます。その際、重要なのが推進体制です。ビジネス・業務部門、管理部門、開発部門などプロジェクトに応じて、必要な横断組織を作る必要があります。
みずほ証券の社内文書検索システムの事例では、事務企画部、経営企画部、ITサービス・プラットフォーム部、デジタル戦略部がワンチーム体制で臨み、成果を上げました。
生成AIの進歩はめざましく、ハルシネーションの発生頻度も下がりつつあるものの、ゼロにはならないのが現実です。その前提で導入領域や導入手法を検討することが重要です。対顧客サービスへの利用の事例として紹介した、三井住友カード、みずほ銀行、MILIZE、楽天証券の事例はそのヒントとなるはずです。
生成AIの利用価値はすでに実証されており、金融庁も「チャレンジしないリスク」に問題意識をもっています。上記のリスクの部分も含め、利活用・導入に関するガイドラインを早期にとりまとめ、積極的な利用を検討する局面に来ているといえるでしょう。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。