執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
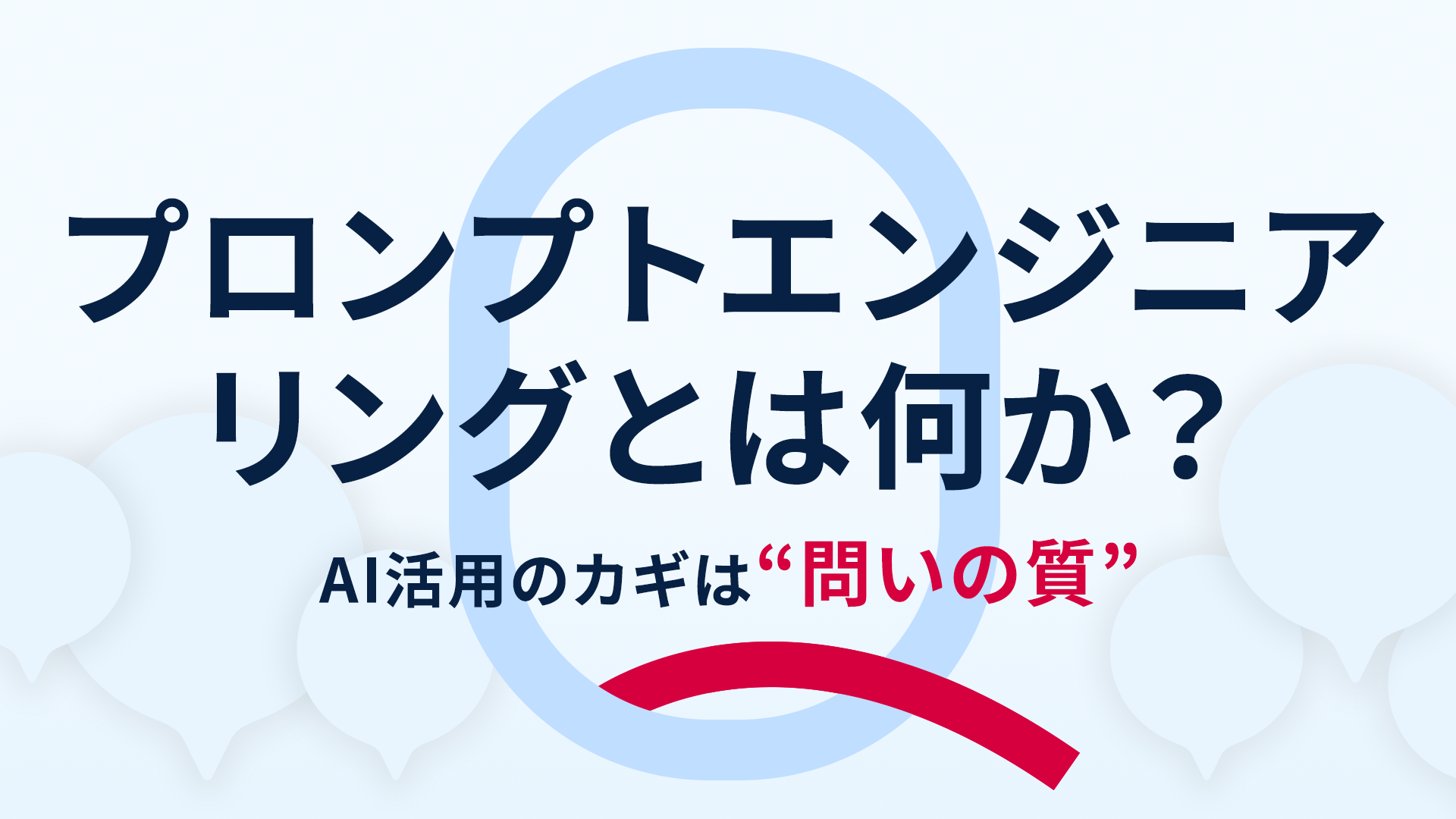
生成AIを導入しても、「なぜかうまく使いこなせない」「出力にムラがあり業務に活かせない」──そんな声が現場から上がってきた場合、フォーカスすべきは、AIの使い方ではなく、「どのようにAIに問いかけるか」というプロンプトの質です。以下は「会議資料を要約する」という同じタスクに対して、プロンプトの設計次第で出力結果にどれほど差が生まれるかを比較した例です。
プロンプト比較例:会議資料の要約指示
評価
一見すると情報量は多いものの、文が冗長で要点が整理されていません。何を伝えたいのかが曖昧で、読み手が目的に応じて判断するには不向きな出力。特に経営層向けの報告としては、「読みやすさ」や「構造の明快さ」が欠けており、活用が難しい印象です。
評価
箇条書きで構成されており、各ポイントが明確に整理。論理的かつ簡潔で、経営層が迅速に状況を把握できるよう工夫されています。プロンプト内で「誰に・何のために・どのように要約するか」を具体的に示したことで、出力の質が格段に高まっているのがわかります。
プロンプトの設計精度が成果を左右するという点は、政府資料においても示されています。デジタル庁が2023年に公開した資料「ChatGPTを業務に組み込むためのハンズオン」では、生成AIの出力をビジネスに資するものにするための、実務的な指針が示されています。プロンプト設計において、現場でも取り入れやすい3つのポイントを取り上げました。
これらの工夫は一見すると、単なるテクニックのように見えるかもしれませんが、プロンプトエンジニアリングは、AI活用のTipsにとどまりません。どのように問いかければ、目的に合った成果が得られるかを逆算する、きわめて実践的な「問いかけの設計」です。業務の成果を左右する設計スキルなのです。

生成AIの成果は、どのように問いを設計するかにかかっています。では実際に、どんな要素を意識してプロンプトを構築すればよいのか。プロンプト設計の基本フレームと活用例を通じて、現場での実践イメージを具体的に掘り下げていきます。
欧州の技術系団体EFCAのレポートでは、プロンプトの設計を以下の6要素に分類・体系化しています。
EFCAは、これらの要素を明示的にプロンプトに盛り込むことで、出力の精度・再現性・ナレッジ化のしやすさが飛躍的に向上すると指摘しています。
前章で「曖昧な設計」として紹介したプロンプト「この資料を要約して」は、この6要素に沿って再構成すると、以下のようになります。
プロンプト設計にわずかな工夫を施すだけで、生成AIの出力は精度・再現性・業務適合性の面で大きく洗練されることがわかります。
では、こうした設計力を業務現場でどう活かすことができるのでしょうか。以下では、職種や目的別に、よくある課題とそれに対応するプロンプトの構成例を紹介します。日々の業務と照らし合わせながら、設計のヒントとして活用ください。
【営業・マーケティング】ペルソナ別の提案文構築
【経営企画・事業戦略】施策要約と意思決定支援レポート
【情報システム・社内FAQ】操作マニュアルの生成
【カスタマーサポート】クレーム対応文の構成
生成AI活用における大きなボトルネックは、プロンプト設計の属人化です。設計ノウハウが個人に依存したままでは、出力の品質や再現性が安定せず、組織全体として成果を出しづらくなる現場もあります。
プロンプトエンジニアリングを個人の工夫にとどめないこと、そして組織で共有・再利用・標準化できる仕組みへと昇華させることが、業務の質の底上げと成果の安定化につながります。
プロンプトエンジニアリングにおいては、レビューやディスカッションも効果的です。出力の内容を確認するだけでなく、「その問いは、目的に対して最適だったか?」という観点から見直すことが大切です。プロンプト設計に関する思考や知見を組織に蓄積し、プロンプトを改善していく文化を醸成しましょう。レビューが定着することで、生成AIの活用を一過性に終わらせず、文化として根付かせることができるのです。
プロンプトのテンプレート化やライブラリ整備といったナレッジ共有の仕組みは、以下のような効果をもたらします。
たとえば、「施策要約」「クレーム対応」「商品提案」といった定型的な業務に対して、成功プロンプトとその出力例をセットで共有するだけでも、実践的な教育素材やOJT資源として活用できます。さらに、リスキリング施策と組み合わせることで、プロンプト設計力を組織的に育成するための基盤としても機能します。
プロンプトエンジニアリングは、メンバー個々のスキルアップにとどまりません。今や、組織の業務ガバナンスの一部としても位置づけられつつあります。IPA(情報処理推進機構)が公開する「DXリテラシー標準(DSS-L)」では、プロンプトの設計スキルを業務ツール活用に必要な基本スキルとして明示しており、今後のリスキリング領域の中核として注目されます。
さらに、内閣府が2024年に策定した「AI事業者ガイドライン案」では、プロンプトエンジニアリングは生成AI特有のリスク(情報漏えい、バイアス、誤情報など)を制御する技術要素として位置づけられています。プロンプトエンジニアリングを体系的に整理し、組織内で共有・運用していくことは、成果を引き出すためのスキルであると同時に、品質・安全性・再現性を支えるガバナンス設計そのものでもあります。これは組織としての責任に直結するテーマであり、避けては通れない課題になりつつあります。
ここまで見てきた通り、属人化を防ぎ、テンプレートの整備やレビュー制度、ナレッジの蓄積を通じて、プロンプト設計を再現可能な仕組みとして昇華させていくこと。さらに、それをリスキリングや業務ガバナンスの一環として位置づけ直すことは、企業全体のAI活用基盤を強化するうえで欠かせません。
自社の知識をいかにAIに渡し、それをどのように価値へ変換していくか──。生成AIを戦略的に活用することが、デジタル時代における競争力の源泉になります。
では、組織としてプロンプトエンジニアリングに向き合うには、何から着手すればよいのでしょうか。以下に、すぐ実践できる具体的なアクションを3つ挙げます。
生成AIは、答えを出してくれるだけのツールではありません。プロンプトエンジニアリングという視点を加えると、向き合っている事業、業務に関する問いを鍛える「ビジネス思考のパートナー」にもなります。
チームで問いの質を高め、プロンプトの設計を共通化することで、AIを使いこなすだけでなく、組織の形式知・暗黙知を資産に変えることができるでしょう。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。