執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
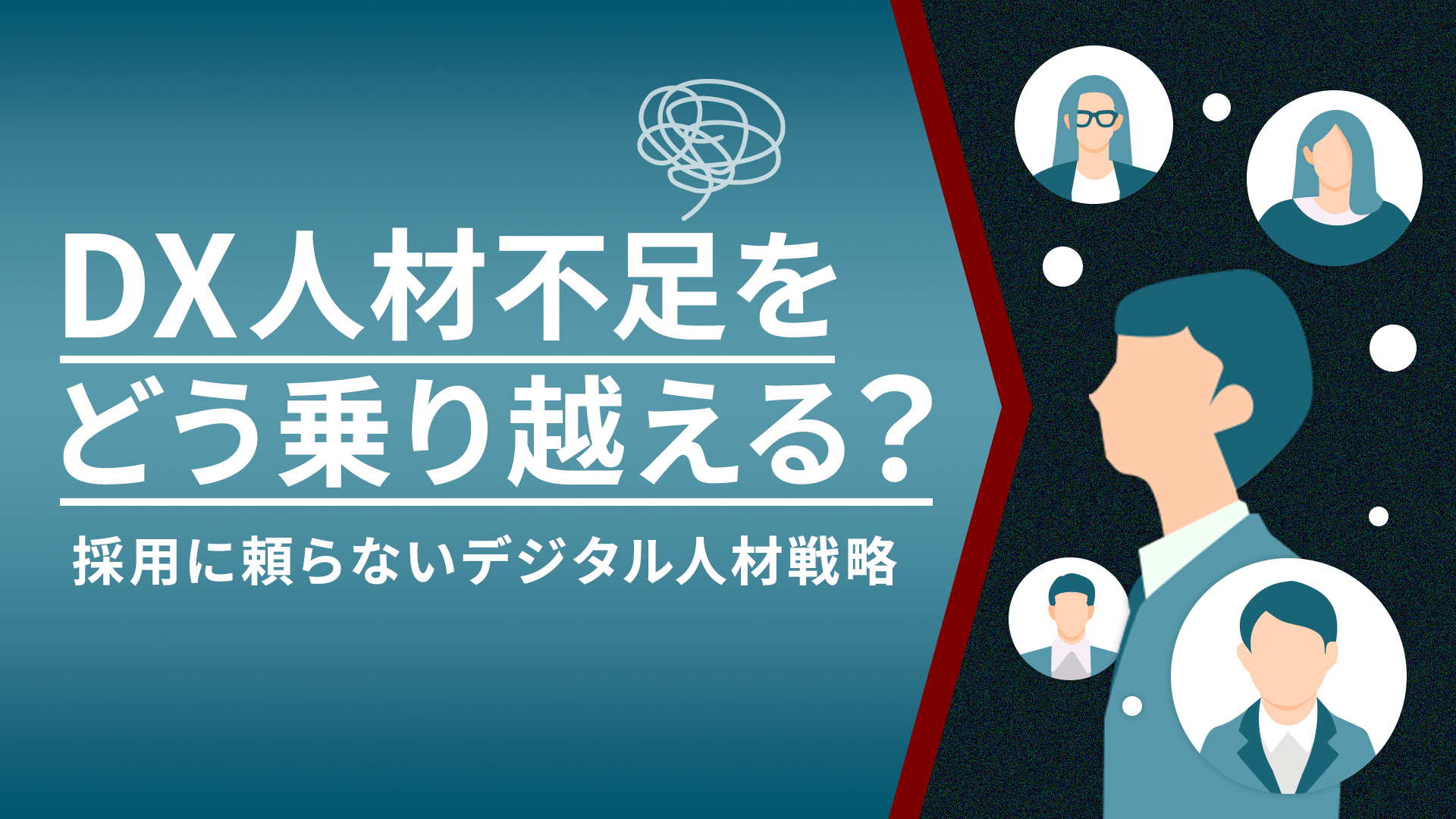
DXの現場では、「人材を採用したはずなのに進まない」「経験者を入れてもチームが動かない」といった声が後を絶ちません。そして、採用に成功してもプロジェクトが思うように進まず、期待されたスキルが現場で発揮されないケースも目立ちます。表面的には人材不足に見えても、その本質は、構造の不整備や役割設計の曖昧さにある──そうした兆候が各所で現れ始めています。
IIJが2025年4月に実施した調査によると、特にDX部門、エンジニア、情報システム部門といったDX推進の現場における人材不足感は深刻で、回答者の約8割が人材が足りていないと回答しました。
これは企業の実態とも一致しています。IPA「DX白書2023」によると、日本企業の約85%が「DX人材の量が大幅またはやや不足している」と回答し、充足しているとした企業はわずか10.9%にとどまりました。一方、米国企業では約73%が「DX人材は充足している」と回答しており、日米間で人材の充足感に大きなギャップがあることが示されています。

この違いは、単なる採用数の差ではありません。人材を戦力として機能させる仕組みの有無が、日米の結果に直結しています。日本企業にいま必要なのは、採用することではなく、「リソースを動かす」視点です。今あるリソースでいかに戦うか。その設計と実行戦略がDXの成否を分けます。
ここでは、DX人材のリソースの配置や役割分担が適切に機能していない背景にフォーカスします。経済産業省が発表した「DXレポート2.1」では、ユーザー企業とベンダー企業の関係性が低位安定に陥っている。つまり、「ベンダーに任せる」「決められたことを遂行する」関係が固定化することで、変化対応力を欠いた体制になっていると指摘されています。
本来なら柔軟に動くはずの人材が、契約上の制約や責任範囲の曖昧さによって自由に動けず、機会を活かせない。人はいるのに動かない──という構造こそが、DXを止める見えない足かせになっているのです。
この障壁を乗り越えるための実践的な指針が、「DXレポート2.2」で提示されています。ここでは、多重下請け構造や人月単価に基づく調達慣習がDX推進の障害だと明記されており、単なる人員増ではなく、契約形態の見直し、責任の再整理、チーム体制の再構築といった具体的なアクションの必要性が強調されています。
「DXレポート2.1」が提示したのは、なぜ変わらなければならないのかという課題の全体像です。対して、「DXレポート2.2」は、どう変えていくのかという実行段階に踏み込んだアクションガイドです。人材が活かされる組織とはどうあるべきか。そのヒントが、ここに集約されています。
DX人材をめぐる諸課題を議論するうえで、見過ごせない前提があります。それは、DX人材とは誰を指すのか、という定義です。この点が曖昧なままでは、採用も育成も、一貫性を欠いた断片的な対応に終始することになります。
経済産業省とIPAが策定した「デジタルスキル標準(DSS)」では、DX推進を担う人材を5つの類型に分類し、それぞれに求められるスキルや役割を明確化しています。たとえば、全体構想を描くビジネスアーキテクト、データ利活用を担うデータサイエンティスト、UXを設計するデザイナーに加え、ソフトウェアエンジニアやサイバーセキュリティなど、専門性ごとの人材像が定義されています。
さらにDSSでは、より実務に即した職種として、プロデューサー、UXデザイナー、アーキテクトなど、現場で必要とされる主要なロールも提示しています。これらを併用することで、自社のDX推進において、どの役割にどのスキルを備えた人材が必要かを具体的に描きやすくなるのが特長です。人材像を明確にすることが、人材戦略の設計精度を高めることにつながるのです。
DX人材の定義は、技術や社会環境の変化にあわせて、常にアップデートが求められます。なかでも、生成AIの急速な普及は、人材に必要とされるスキルセットやマインドセットを大きく変えつつあります。
経済産業省が2023年に発表したレポートでは、生成AI時代に求められるDX人材の資質として、「変化を恐れず学び続ける姿勢」「問いを立てる力」「仮説検証力」「プロンプト設計力」「AIのリスク理解(倫理・情報管理)」などが挙げられました。技術に通じるだけでなく、ビジネスと技術をつなぎ、戦略的に活用できる人材像が明示されています。
こうした傾向は、三菱総合研究所が2025年に実施した「DX推進状況調査」にも表れています。同調査では、データ分析ができる人材よりも、ビジネス課題を理解し、分析を施策に結びつけられる人材が求められていることが示されました。求められているのは、ツールの操作ではなく、現場と課題を結びつける実践力。それは現場の実感とも重なります。
今後のDXを支えるのは、単に技術的な知見を持つだけでなく、それをビジネス成果へとつなげられる担い手です。そのためにも、誰に何を任せるかを見極める定義づけが、人材戦略の出発点になります。
Gartner Japanが2024年に発表した調査によると、3年以上にわたりDX人材の育成に取り組んだ企業でも、成果を実感しているのはわずか24%にとどまるという結果が示されました。育成に時間を投じても、活用の設計がなければ成果にはつながらないという現状が浮き彫りになっています。
その背景には、「育成した人材が適切に配置されない」「実践の機会が用意されていない」「成果が評価に反映されない」といった、人材運用の不全が存在します。人材の定義や育成だけではなく、配置・活用・評価までを含めた運用フェーズの戦略が重要になるのです。
デジタル人材の社内確保が難航するなか、外部のプロフェッショナル人材を組み込む体制が一般化しつつあります。経済産業省が2025年に公表した「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き」でも、外部支援を活用しなければDXは動かないという現場の実感が示されました。
準委任型での伴走支援、ITコーディネータとの戦略協議、外部トレーナーによるOJTの導入など、内製と併走する支援モデルへのニーズが着実に拡大。かつては慎重に扱われていた外部連携も、DXの実装段階では前提条件として捉えられるようになっています。
こうした共創型アプローチは、単なる業務委託ではなく、ノウハウを社内に定着させる仕組みとして意味を持ちます。外部人材の活用は、人材不足だから頼るという消極的な選択ではなく、「必要なリソースと連携をどうおこなうか」を設計する前向きな経営判断へと変わりつつあるのです。
IPA「DX白書2023」によれば、DXで成果を上げている企業ほど、「外部契約」「社員紹介」「中途・新卒採用」など、複数の人材獲得手段を組み合わせている傾向が見られます。

この傾向は、米国企業においてさらに顕著です。特定技術を持つ企業や個人との契約が一般化し、育成と外部連携を両立させるハイブリッド型の戦略が定着している傾向がうかがえます。社内にない専門性を外部から取り込み、知見を社内に定着させる──その循環が、継続的なDX推進を支える基盤となります。

生成AIの導入が加速するなか、その運用フェーズにおいても、外部プロフェッショナル人材の活用が広がりを見せています。みらいワークス総合研究所の調査によると、大企業の27.6%が「生成AIの導入・活用支援を外部人材に依頼するようになった」と回答しました。AI利活用の支援や業務棚卸、プロセスBPR(業務再構築)など、上流工程にあたる設計フェーズを外部に委ねるケースが増加傾向にあります。社内に十分な知見が蓄積されていない領域では、外部の視点や経験を活用が求められます。
ただし、業務をただ外部に委託するだけでは、ノウハウやスキルが社内に蓄積されないまま終わってしまう懸念があります。支援を受けるなかでは、知見や成果をいかに自社内に残すかという視点が欠かせません。
たとえば、成果物を共有可能な形式で納品してもらう、現場担当者がOJT形式でプロジェクトに加わる、運用ノウハウをドキュメント化する――こうした仕組みの有無が、支援の成果を組織に確実に定着できるかどうかを左右します。
外部人材との連携も、その場限りの補完ではなく、プロセスを通じて組織が成長する機会として捉えることが重要です。生成AIのような新たな領域に踏み出す際には、外部への業務発注にとどまらず、ナレッジの引き継ぎ~社内定着まで見据えた「共創型の契約」として考えていくべきなのです。
人的リソースの課題は、採用や育成といった個別施策にとどまりません。DX推進におけるリソースの再構築には、現場任せではなく、経営レベルでも関与と設計が不可欠です。
経済産業省が2024年に改訂した「デジタルガバナンス・コード3.0」では、DX推進を「IT部門に委ねるのではなく、取締役会や経営層が主体的に担うべき経営課題」と明確に位置づけました。単なる業務のデジタル化ではなく、経営戦略とデジタル施策の一体化が求められる時代に入ったといえるでしょう。
同コードでは、「人材育成・確保」も独立した重要項目として明記されており、社内教育、外部人材の活用、リスキリング施策、評価制度の整備など、人材戦略全体を経営課題として捉えるべきことが強調されています。人的リソースは、コストではなく投資であるという視点への転換が、DXの持続力を支えるのです。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。