執筆者紹介

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。
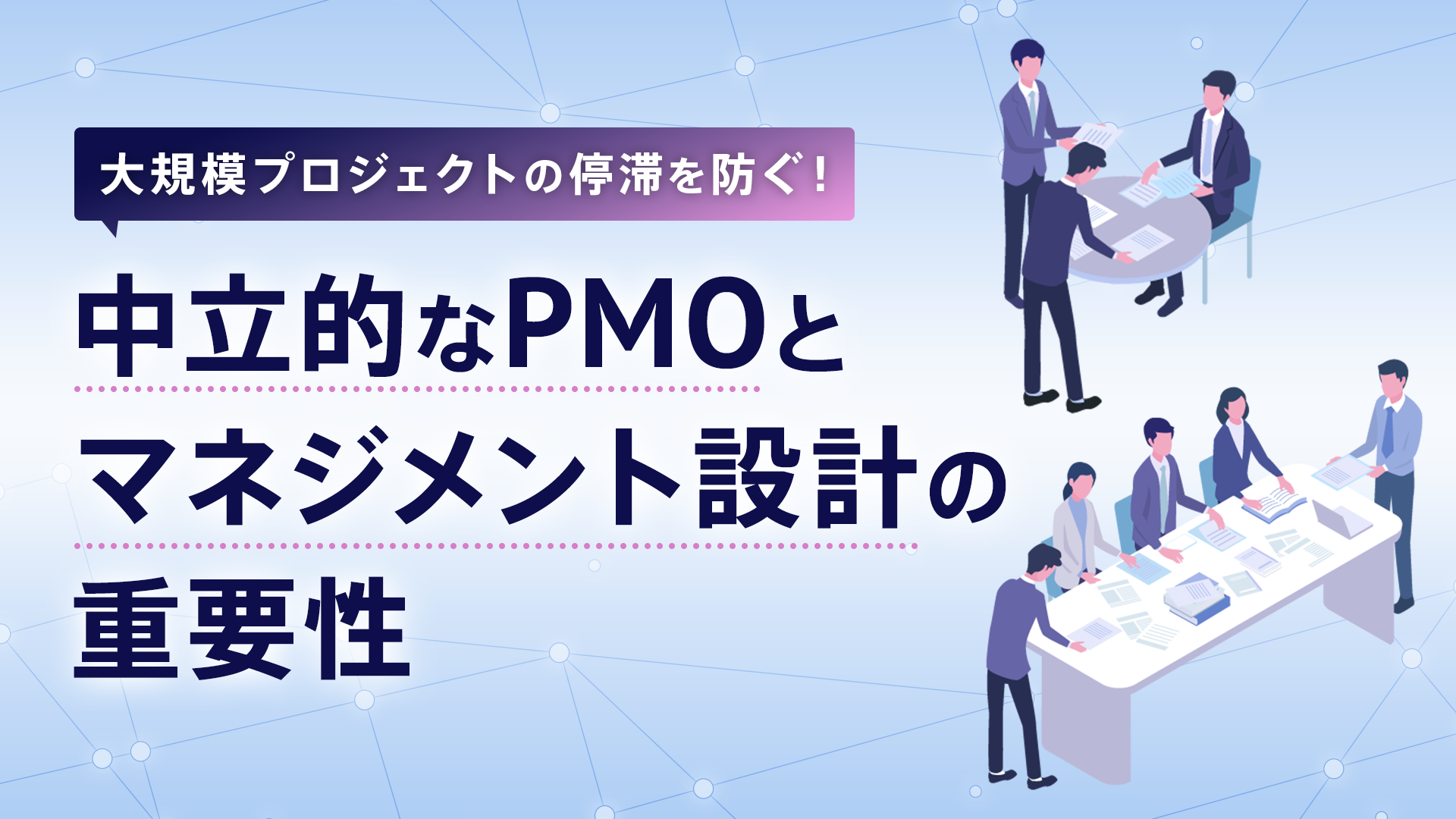
「関係者が多すぎて意思決定に時間がかかる」
「一部の部署が非協力的で前に進まない」
「PMの役割が曖昧で判断が先送りになる」
こうした声は大規模プロジェクトにおける、よくある課題です。これは単なるスケジュール遅延ではなく、組織間の温度差や役割の不明確さから起きることも多いです。さらにこういった声があちこちで上がればプロジェクトが停滞する状況を招いてしまいます。今回は、大規模プロジェクトあるあるを乗り越え、停滞していたプロジェクトが動き出せるよう、具体的なマネジメント設計例や体制構築のアプローチを紹介します。
大規模プロジェクトが停滞する要因は、仕組みと組織に起因するプロジェクト構造にあります。
プロジェクトの規模が大きくなればなるほど、チーム、関係部署、関係者が増えます。そうなることでそれぞれの利害や目的も複雑化します。その結果、プロジェクトとして何を最優先すべきかの共通認識を持つことが難しくなり、決定が遅れることも増え、プロジェクト全体の動きが停滞しがちになります。
実際に現場で作業をするチームの状況が上層部に共有されないままプロジェクトが進むと、現場との間に温度差が生じます。現場の進捗だけでなく、課題やトラブルが上層部に正確に伝わらないまま意思決定がおこなわれると、現場の実態と方針にズレが生じることになります。この温度差が、現場のモチベーション低下や作業の手戻りを引き起こし、プロジェクトのスピードを鈍らせる大きな要因となるのです。
個々のプロジェクトによってPMの権限や役割が異なるケースもあるかもしれません。今のプロジェクトと前回関わったプロジェクトで差異があることもあり得ます。プロジェクトの成功やスムーズな進捗にはプロジェクト開始前にPMの明確な権限や役割の範囲が決定されていることが理想ですが、曖昧な場合は意思決定が後手に回ることや、スケジュール調整が滞ることもあります。組織やプロジェクトごとに異なる運用ルールも混乱を招き、PMの役割が十分に機能しないことも少なくありません。
常にプロジェクト全体がどういう状況であるかが共有されていなければ、自分たちが関わっている業務にしか目が向かないと考えてしまうのも無理はありません。全体の状況や目的が共有されていないと、それぞれのチームが自チームの仕事だけに集中し、プロジェクト全体への関心や責任感が薄れてしまいます。その結果、連携不足や情報の断絶が起こり、プロジェクトがスムーズに進まなくなる原因となります。

進まないプロジェクトで起こるトラブルや課題を乗り越えるために必要なものは、巻き込み力のあるマネジメント設計とPMO(Project Management Office)機能の構築です。ここでは、プロジェクト停滞の解決のカギとして巻き込みのための3つの設計視点をピックアップして解説します。
誰が・どの業務を・どこまで進めているかをプロジェクトメンバーが共有できる仕組み(可視化ツール、定例MTGの設計)を整備しましょう。大規模だからこそ、情報の透明性の高いプロジェクト進行が必要です。自分たちの関わっている業務にしか目が向かないと他チームで抱えている課題やトラブルに気付くことができません。
この見えにくさが、認識のズレや責任の押し付け合いを引き起こし、プロジェクトの停滞につながるのです。これを防ぐために、業務の進捗状況や課題を可視化できるツールや仕組みを設け、情報が常にオープンに共有されている状態を作りましょう。また、ツール上の可視化だけではなく、定期的なミーティングを通じて部門間の情報連携を習慣化し、進行状況とともに周囲のチームの状況を大まかにでも把握して「プロジェクト全体がどうなっているか」という意識を持てるように促します。
大規模プロジェクトでは、関係者の利害や立場が多様であるがゆえに、意思決定に時間がかかる傾向があります。だからといって、すべてをトップダウンで進めてしまうと現場に当事者意識が生まれず、やらされ感からプロジェクトの実行力が弱まってしまうことも少なくありません。重要なのは、各ステークホルダー(プロジェクトの意思決定や実行に関与する部門や担当者)が意見を出しやすい発言の場を設計することです。
単なる会議体の設定ではなく、「どのタイミングで、誰が、何を発言できるか」をあらかじめ設計し、プロジェクトに関わる全員が自分ごととして参加できる構造をつくる必要があります。つまり、双方向で発言できる流れを意識的にデザインすることがプロジェクトに関わるメンバーの納得感と実行力につながります。
PMOなどの中立的な存在がその調整ハブとなり、各部門の意見を整理・翻訳して共有すれば対話の場がさらに機能しやすくなります。結果として、違いを認識しながら建設的な合意形成を進める土壌が整います。
現場と上層部の意見の食い違いやぶつかり合いは、大規模プロジェクトにおいて避けがたい現象です。それを回避するためにも、人や組織に偏らない第三者的視点を持つPMOの機能を用意し、対話と調整のハブの役割として機能させて合意形成を進める仕掛けを構築しましょう。PMOは、PMをサポートし、プロジェクトの進行を支える専門組織です。
スケジュール、品質、コストなどのマネジメントをPMとチームなどの間で客観的に管理しつつ、部署横断をしながら調整やリスクの早期検知にも貢献します。PMOが適切に機能することでプロジェクトの進行に一貫性と安定感が生まれ、さらに各部署の意見を整理し、合意を形成するためのファシリテーションや情報の橋渡しをする役割を担います。PMOがあることで誰か一人の意見に引っ張られることや、何も発言できなくなるリスクを避けられ、組織全体で納得感を持ってプロジェクトを進めることができます。
実際のプロジェクトマネジメントの事例を紹介します。意思決定の加速として何をしたのか、合意形成のポイントは何だったかなどを参考に、今後のプロジェクトマネジメントに取り入れてみましょう。
メンバーズは、JR西日本SC開発株式会社さまのショッピングセンター事業の統括部門であるカンパニー統括本部にて、CRM領域として、アプリ機能開発及び、CRMの推進(BI構築含)などにおけるPMO/PdMによる支援、ルクア大阪事業本部では、マーケティングコミュニケーション部門における会員施策・デジタルメディア活用などの支援をおこなっています。
オーナーシップを持ったチームづくり。PMO/PdMによるDX推進の舞台裏
メンバーズは、KDDI株式会社の「オンラインチャネル変革プロジェクト」を支援しました。本プロジェクトでは、UI・UXデザインとPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)の支援を通じて、オンライン機種変更の申し込み完了数増加などを実現し顧客体験の最適化に貢献するとともに、プロジェクト推進のサポートやデザイントレーニングなどにより、DX推進の内製化や人材育成に貢献しています。
KDDIの「オンラインチャネル変革プロジェクト」を伴走支援!UI・UXデザインとPMO支援を通じて契約者数の増加など顧客体験向上を実現
大規模プロジェクトにおける運用スタイルやPMOに対する思い込みや誤解もいくつかあります。以下にその誤解に対する正しい見解をまとめてみました。
大規模プロジェクトにPMOを入れることによってPMを補佐する組織・人材が増えることで追加されるコストが気になる方もいるかもしれません。しかし、PMOはプロジェクトを円滑に進ませるための組織なので、むしろ推進ロスや再調整の手戻りを防ぐための投資であり、中長期的にみればコスト削減に寄与する仕組みになります。
PMOを導入することのメリットは、単に人を増やすことではなく、プロジェクト全体の見通しを良くし、課題を早期に発見・対処できる体制を構築できることにあります。プロジェクト全体を横断的な視点でマネジメントすることで、不要な会議や作業の戻り、意思決定の遅延といったロスを大きく減らすことができます。
近年、PMOという名称だけが独り歩きをし、実際には具体的な業務範囲や役割が定まっておらず上手く機能していないケースも存在します。そういった状態が、実体のないPMOや単なる事務局とみなされ、PMや現場から期待されない存在になってしまいます。
機能するPMOを設計するためには、現場の動きやプロジェクトの目的を理解し、論点を整理して対話できるスキルを持った人が求められます。形だけで終わらせず、組織内で実効性のある設計をすることで、PMOは動かないプロジェクトに対するもっとも頼れる推進エンジンとなり得るのです。
トップダウンだけでは関係部署の当事者意識が育たず、継続的な合意形成が難しくなりがちです。特に大規模プロジェクトでは上層部と現場をつなぐ役割としてPMOが重要です。現場ごとに状況や課題が異なるため、一方的な指示だけでは柔軟な対応ができず、かえって現場との温度差が広がってしまいます。
PMOはその橋渡し役として、PMの方針を適切に翻訳し、現場が納得しやすい形で共有することが重要です。また、現場の課題やリスクをPMに分かりやすく伝える役割も担います。つまり、PMのマネジメントを現場に届く形に変換することでプロジェクトメンバー全体が同じ方向を向いて動くための土台を作ることができるのです。
大規模プロジェクトの停滞はメンバーのやる気やスキル不足ではなく、構造と設計の問題であることが少なくありません。案件に関わる一人ひとりがプロジェクト全体に高い関心を持って動かす仕組みを設計することが成功の近道です。さまざまな関係者や部門をまたぐ大規模プロジェクトだからこそ、巻き込み力と中立的推進体制を構築してプロジェクトを確実に動かしましょう。

株式会社メンバーズ
「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。